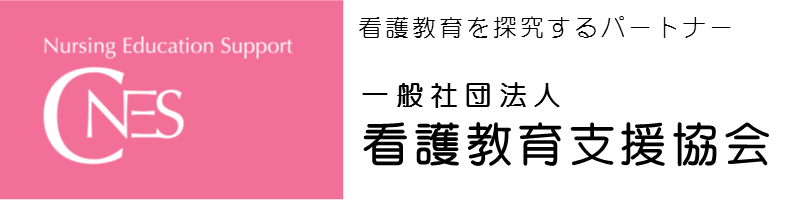かき氷
梅雨も明けて、真夏の暑さが続いている。コロナ禍だったからだろうか。「夏」って何をしていたかな、みたいな気持ちになる。夏祭り、浴衣、夏休み。スイカ、かき氷。そう、かき氷。
いよいよ、入れ墨彫師の患者さんは、話せる日もあれば、話せない日もあるといった状況になった。(「時空を超えた交流」第1話。)
「ところで、どなたに会いたいのですか?私が代わりにお電話しますよ。」と言うとしばらく深刻そうに考えていた。ペンと紙を貸してと言うので、差し出すと電話番号を書いた。「覚えているんですね!よかったです。じゃあ、お電話しておきます。」と言うと、私の腕つかんで「やっぱりやめとく。」「ん?会いたい人なんでしょう?」「・・・・・」彼は、やたらと思案していた。いつもの顔ではないので、「○○組の親分みたいな人ですか?」と言うと、真顔で「違う!」と言った。ここまで、じらされると私も是が非でも聞きたくなった。しかし、問い詰めると、答えなくなるのは世の常である。「わかりました」と言って、退室しようとした。
彼は、私の背中に向かって「あのな、人妻やねん」と言った。想定外の答えに絶句した。これはもう、私一人でどうしようもない。主治医や看護師長さんを交えて話し合いをした結果、相手の同意があれば、面会に来てもらうということになった。
40歳半ばの女性らしい。電話をすると、とても驚いており、連絡がつかないことで心配していたようだった。彼女はさっそく、面会に来てくれることになった。彼に伝えると目を真ん丸にして喜んでいた。舌を出して手に唾をつけて、髪の毛を整える真似をしたり、ネクタイを直すしぐさをしたりしてとにかく上機嫌だった。
彼女が来た。彼の「人妻やねん」の言葉から想像していた私の「人妻」のイメージからはるかに違う人物が来た。まず、目に飛び込んできたのだが艶のないロングヘアだ。白髪と黒髪と茶髪が混合した何ともオリジナリティあふれるヘアスタイルだった。顔は全く化粧をしていなかった。とても細身の体にヒョウ柄のTシャツと模様の入ったジーンズのコーディネート。手には大手家電店の開店セールで配布していたバッグを持っていた。我が家にもあるので間違いない。久しぶりに彼氏に会うというのに化粧もせず、おしゃれとも言い難い身なりだった。「本当に連絡が取れず心配していたのか。急いできてくれたのか。」と思った。私は挨拶をして、部屋に案内した。挨拶をした際、彼女は愛想よく笑ってくれた。ちょうど左の上側の切歯が抜けていた。私は、彼の前で笑うときは「手で口を押さえたほうがいい」と余計なことを思った。
彼女を部屋に連れて行ったとき、二人は久しぶりの再会に手を取り合っていた。彼女が「やせたね~」と声をかけると、彼は間髪入れず「ダイエットしてるねん」と言った。私は、お邪魔のようだから、黙って退室しようとすると、二人が満面の笑みで「ありがとう」と言ってくれた。彼女は左の上側の切歯がないから笑わないほうがいいと思ったが、もうどうでもよくなった。まず、彼は、彼女の歯の抜けていることを気にしていなかった。
しばらくして、彼女がスタッフルームに来て「食べたらあかんものあるの?」と聴いてきた。「特にないですよ」と答えた。「売店でアイスクリーム買って来ようと思うんだけど」と言うと、たまたま私の隣にいた主治医が「いいですよ、食べてもらって。屋上とかに行ってもいいですよ」と付け加えた。主治医は簡単に言ってくれるが、彼を屋上に連れていくには、ベッドごと行くほかない。ストレッチャーに移すことも困難なほど骨に転移しており、痛みを誘発させるからだ。
彼女は売店で、イチゴのかき氷を買って来て「屋上で食べます~」と言ってにっこり笑った。私はいちいち欠損歯が気になった。私は主治医に「先生もついていってくださいね」と言って、主治医と私と患者さんとその彼女とで屋上に行った。もちろんベッドごとの大移動だった。
真夏のいい天気だった。陰になっている部分にベッドをとめた。彼女は、1つのイチゴのかき氷を先に自分が食べ、次に彼に食べさせ、かわるがわる食べていた。突き抜ける青空と入道雲、見下ろすと緑地公園がある。イチゴのかき氷をかわるがわる食べながら話をしている。微笑ましい時間だが急変することも考えられるので、少し離れたところで主治医と私は二人を眺めたり、目をそらしたりしていた。最期に会いたい人に会えてよかったと思った。ポケットに手を突っ込んだまま壁にもたれている私よりも若い主治医は、この光景をどのような感情で見ているのか、横顔だけでは何を考えているのかわからなかった。
そういえば、私の腕に入れ墨を描きたいと言ったパンジーの花は、彼女のことだったのか。彼女をパンジーと言うには、ほっそりしすぎている。それに何度も言うが笑わないほうがいいような気がする。花にたとえるなら、ネジバナのようにシュッとした人だ。彼が最も愛した女性なのだ。
「さあ、そろそろ病室に戻りましょうか」と主治医が声をかけた。二人は手をあげて「OK」と言った。
シーツには、かき氷をこぼした赤い点々と甘いにおいが残されていた。
それから、1週間もたったのだろうか。彼は、夕方にあっけなく旅立っていった。彼女に連絡をしたが、「今日は出ていくことはできません」と言った。淡々とした言葉遣いが、かえって爆発しそうな感情を抑えていると思った。私たちスタッフは「そうだな、晩御飯くらいの時間だからな」と話を収めた。ご遺体は、病院から自治体に連絡し引き取りに来てもらうことになった。
孤独死をネガティブに言う人もいる。私は、周りに誰かがいるとかいないとかと言うよりも、死んでいく前の限られた時間、何ができるのか、何を思うのか、誰といるのか、どんな空間なのかを大切にしたいと思う。このことは、みんな違っていていい。決まっているものではない。
大切な人が死んでいった後、悲しむこと、嘆くこと。会いたい人に会いたいと思うこと、ためらう気持ち、双方を思いやる気持ち、思いやりすぎてモヤモヤする気持ちは、『万葉集』の時代から変わっていない人間の普遍的な感情だとつくづく思った。ちなみにかき氷は、平安時代の『枕草子』に「けづりひ(削り氷)」と記されているらしい。
時代の流れについていけないと思っても、変わっていないものもあると思うと、それはそれでいいのかもしれないと思う。

「看護」とは何かについて考えていくことを意図として、「看護師日記」を書くことにしました。私の看護師、看護教育の経験に基づいて表現していますが、人物が特定されないように、また文脈を損なわないように修正しています。