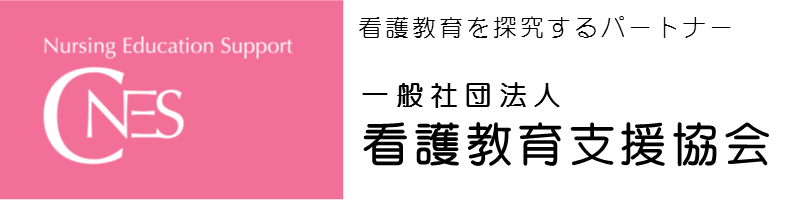点数(知識量)の開きと卒後の新人看護師教育の課題
114回国家試験の一般状況問題の足切り点は、150点台前半と言うところで落ち着きそうです。しかし、楽々と合格する人と、今、崖っぷちに立たされているような気持ちになっている受験生がいることが現実です。
私は、楽々と合格した人が素晴らしいと言っているわけではなく、崖っぷちに立たされている人や浪人して受かる人をを非難するわけではありません。
そんな皆さん方が、同じ「新人看護師」として院内教育や施設内教育の標準化にのせられてしまうことに違和感を覚えるのです。
現代の大学生たちは、アクティブラーニングやITを活用した学びに慣れ親しんだ世代
従来の講義型教育よりも、主体的な学びや、デジタルツールを活用した教育環境を経験してきました。
そんな学生たちが、看護師国家試験を終えてみるとトップ群と点数の低い群と大きな差を生んで合格し、看護師として就職します。
それは、たかがペーパーテストですから、その知識量と患者さんやその家族やチームメンバーとから信頼を得る量と比例はしないと言えるかもしれません。むしろ就職した後、必要な力量は「コミュニケーション力」だとおっしゃる方も多くいらっしゃいます。
では、就職した後、どんな教育によって、技術習得、多職種や患者やその家族とのコミュニケーションに至るまで体得できるのかと疑問を抱きます。
そこで、近年よくあるオンデマンド型教育のメリットとデメリットを整理し、さらに協働が求められる時代に適した院内・施設内教育について提案します。
オンデマンド型教育のメリットとデメリット
メリット
- 学習の柔軟性が高い
勤務シフトが不規則な看護師にとって、いつでもどこでも学べるオンデマンド教育は、大きな利点です。通勤時間や夜勤の合間など、自分のペースで学習を進めることができます。
- 個別最適化された学びが可能
知識の定着度に応じて、必要な部分を重点的に学習したり、理解が難しいところは繰り返し学んだりすることができます。特に、新人看護師や経験の浅いスタッフにとっては、業務の合間でもスキルアップが可能になります。
- 反転学習の活用
事前にオンデマンドで基礎知識を学習し、実際の業務やケーススタディでは実践的な議論を行う「反転学習」の形式を導入しやすくなります。
- 教育資源の均等化
大規模病院だけでなく、中小規模の病院や施設でも、最新の知識やベストプラクティスを学べる環境が整いやすくなります。特に地方の医療機関にとっては、教育の地域格差を埋めることが可能です。
デメリット
- 協働や対話の機会が減る可能性
チーム医療を支える対話力や協働スキルを育む場が減る懸念があります。特に、患者対応や多職種連携のスキルは、実際のコミュニケーションを通じて鍛えられるため、補完策が必要です。
- モチベーションの維持が難しい
自己学習が前提のため、学習習慣が身についていないと、後回しにしがちです。特に、忙しい業務の中で自主的に学ぶ姿勢があってこそ初めて効果を発揮します。
- 実技や実践の場面が不足しがち
リアルな患者対応の経験が不足する可能性があり、シミュレーションやOJTとの組み合わせが不可欠です。
協働が求められる時代に必要な院内・施設内教育とは?
オンデマンド型教育のメリットを活かしながらも、看護師として必要なスキルを総合的に育成するためには、次のような仕組みが必要です。
① ハイブリッド型教育の導入
オンデマンド学習を基礎知識の習得に活用し、
- 院内研修やOJTで実践的な学びを深める
- シミュレーションやケースカンファレンスやケーススタディで協働力を強化する
といった、ハイブリッド型の教育が重要です。これにより、「知識→実践→フィードバック」のサイクルを回しやすくなります。
② 共に育つという文化をつくる
オンラインでの学習が増える一方で、「学びを職場でどう活かすか?」を相談できる環境も必要です。定期的な対話(対等なコミュニケーション)の場を設けることが必須です。
③ チーム医療を意識した学習設計
院内・施設内教育では、看護師単独の学びにとどまらず、医師・薬剤師・リハビリスタッフ・介護士など、多職種との協働を前提とした内容を充実させることが求められます。
例えば、「多職種カンファレンスのロールプレイ」や「患者さんとのコミュニケーションワークショップ」を取り入れることで、実践的なスキルを身につけられます。
④ 学習の可視化と評価
オンデマンド型教育の課題の一つに「学んだことが現場でどう活かされているか分かりにくい」という点があります。学習管理システムを活用し
- どのコンテンツをどの程度学習したのか?
- 学んだことが現場で活用できているか?
を可視化する仕組みを取り入れていく必要があります。
まとめ
現代の大学生はITやアクティブラーニングを活用した教育に慣れており、オンデマンド型教育にも比較的適応しやすいと考えられます。しかし、看護という職業の特性上、オンライン学習だけでは補いきれない部分も多くあります。
そのため、
- ハイブリッド型教育で「知識+実践」の強化
- 「学びの活用」を組織的に支援
- 多職種協働を前提とした院内教育を充実させる
- 学習の可視化を行い、学習効果を高める
といった工夫が不可欠です。
技術が進化する時代においても、「人と人との関わり」を大切にした看護教育が求められています。オンデマンド型教育を活用しつつ、「実践知」を磨ける環境を整えることが、これからの院内・施設内教育の鍵になります。それはすでに働いているスタッフの皆さんの何気ない言動が「組織文化」をつくっていると言っても過言ではありません。組織文化が、日々のさりげない言動に影響しているとも言えます。
114回看護師国家試験のバーダーラインを予測しつつ、同じように学んだ仲間の中で生まれる差異を、どのように実践教育で生かしていくかを考えさせられました。
さまざまな人がスタートラインに立ちます。皆さんの特性が生かされ、社会に貢献できる人材として、まずご自身が「やりがい」をもってますます成長していかれることをお祈り申し上げます。