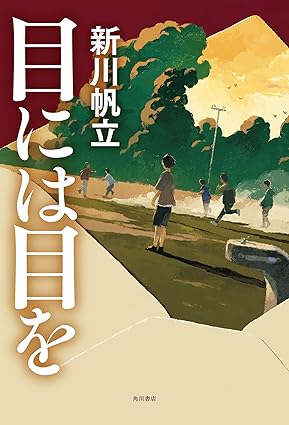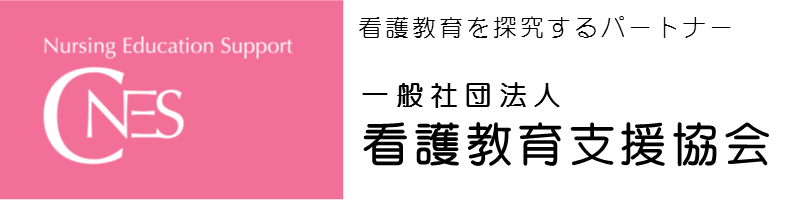はじめに
新川帆立さんの小説『目には目を』は、少年犯罪に関わった六人の少年たちのその後を描く物語です。彼らは重大な罪を犯し、少年院で出会い、社会に戻ったはずでした。しかし過去は消えず、ある者は命を奪われてしまいました。
この物語は「更生とは何か?」という問いを読者に突きつけます。
看護師として読むと、この問いは「人が社会で生きる力をどのように育むか」という問題を考えざるを得ません。
少年犯罪の背景にある「育てにくさ」
作中の少年たちは、一見「本当は良い子」だったと語られます。
しかしその背後には、育てにくさ(発達特性や気質)やボーダーラインのIQ、複雑な家庭環境といった生育歴があります。
例えば、感情のコントロールが苦手な子、学習についていけない子、虐待やネグレクトを受けて育った子――。逆に特に問題はなかったけど友達も多い方だったし・・・・どれもこれも主観的な通りすがりに感じた意見のような軽さを感じます。
これらは本人の努力不足ではなく、環境や発達の特性に起因することが多いのです。
人格形成と「社会で生きる力」
人が成長するには、家庭や学校、地域といった社会的環境から「支え」や「モデル」を得ることが必要です。しかし、作中の少年たちの多くはその支えを十分に得られず、結果として「社会の中で生きる力」を育む機会を失っていました。
看護師として考える「更生」とは、単に罪を償うことばかりでなく、失われていた成長の過程を取り戻す支援だと思います。
「再び社会の中で生きる力」を学び直す機会が与えられるかどうかが、更生に至るのかどうかを分けるのだと思います。
被害者側からは到底受け入れられるようなことではないのかもしれません。その到底受け入れられないほどの傷を受け入れる器としての自己になる過程だと思います。
更生とは「支援とつながりの再構築」
被害者遺族の苦しみは消えません。加害者の少年たちが「本当は良い子」だったとしても、それは正当化になりません。
それでも看護師として思うのは、人が人として生き直すためには、支援とつながりが不可欠だということです。
発達や家庭環境に課題を抱える子どもたちは、家庭(居場所)・教育・地域・医療・福祉――それらが連携して、つなぎ直すことが「更生」の基盤になります。
看護師としての私の気づき
『目には目を』を読み、私は「更生」を次のように捉えるようになりました。
- 更生とは、過去を消すことではなく、不十分だった発達と人格形成を支え直すこと
- 更生とは、社会の中で生きる力を再構築すること
- 更生には、支援者と居場所が不可欠であること
看護師として、医療や地域で出会う子どもたちに対しても、同じ視点が必要だと痛感しました。
おわりに
『目には目を』は、少年犯罪の物語でありながら、人がどう生き直せるのかを問う作品でした。
看護師としての立場からは、少年たちの背景にある「育てにくさ」や「生育歴」を直視し、その中で「社会で生きる力」をどう支えていけるかを考えさせられました。
更生とは、リセットするわけでなく、人としてもう一度生き続け、「罪」というものを認め、感じ、七転八倒しながらも、「生きている」ことに喜べる人になっていく過程そのものなのだと感じました。
私自身が、この時、この瞬間、この状況に置かれたとき、何ができるのだろうか、私は、間違いなく、被害者にも、加害者にもなる一人の人間であることを再確認させられた一冊でした。