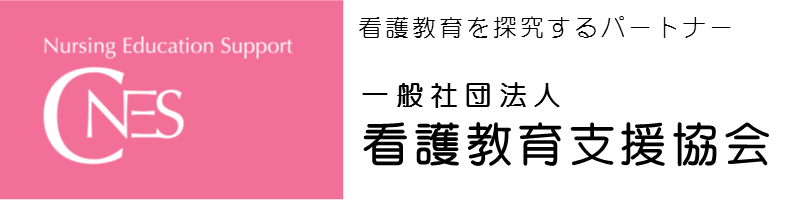映画化されるのかな?その前に読んでおこう!
染井為人さんの『滅茶苦茶』を読みました。読み終えて「コロナ禍が人生を狂わせたのか?」という問いだった。「コロナ禍」、なんだったんだろう。
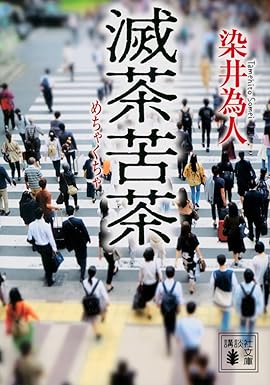
物語には、シングルライフを謳歌していた女性が出会った男性と絵に描いたような危険な恋に落ちていく美世子、県内トップクラスの高校に通いながら過去の級友との再会から道を踏み外していく礼央、経営不振に苦しみ妻と三人の子どもを守るために悪事に手を染めてしまうラブホテルのオーナーの茂一が登場する。
彼らの人生はそれぞれの孤独と欲望と焦りが絡まりながら転落の一途をたどる。そこには常に葛藤があった。「だめだ!」と。にもかかわらず、何度も何度も判断を間違える。やり直せるチャンスや、踏みとどまるチャンスはいくらでもあった。「は~」とため息をつきたくなるほど何度も判断を間違えるのだ。
そして、ラストは各々の人生が交錯する。単なる偶然ではないようにも感じるのだ。
コロナ禍は、多くの人々に孤立や不安をもたらした。何とか保たれていた人間関係や社会との繋がりが希薄になり、誰もが途方に暮れるような状況となった。
仕事を失った、助成金や補助金の対象外となった、経営難が続く・・・・。将来への不安、人間関係の歪み。そうした精神的、経済的な圧力の中で、人はいとも簡単に間違った選択をしてしまう。
私の感想として「人間が崖っぷちに立たされたとき、どんな選択をするか」が問われていたということだ。そのとき、「善であるかどうか」が基準になる。ふだんなら容易に判断できる「善」やその主張が、コロナ禍のような非常時には、その基準さえ見失い、声さえ出なくなってしまう。その逆もある。大声で主張する人や有識者という人の意見に流された。そんな人間の脆さや揺らぎが、この作品には色濃く描かれていた。
本作に描かれた登場人物たちの姿は、私たち自身のすぐ隣にある現実、あるいは自分自身なのかもしれない。「自分ならこうはならない」と言い切れない。誰もがちょっとしたきっかけで崖っぷちに立たされる可能性があることを本作は教えてくれた。
私たちはこれからも不透明で不確実な時代を生きていく。本作を通して「人はなぜ転落していくのか」「その要因はどこにあるのか」を深く考える機会を得ることができた。経済的な困窮、社会的孤立、それでも生きていくという焦燥感。「静かに追い詰めるもの」が人をじわじわと蝕み、保つことのできる理性さえも失わせてしまう。
転落の要因とは、単なる「個人の弱さ」ではなく、環境が個々の選択肢を奪っているのだ。
しかし、底に落ちたからこそ見える世界、これまで感じなかった有難さを知ることができるらしい。
つまり、転落とは、ある種の逆転のエネルギーでもあるのではないかとも感じた。底を見た人間にしか持ち得ない視点や力が、どこかで人生を反転させる契機となる可能性もある。
読後は、その予感があたたかな余韻として胸に灯るのだ。