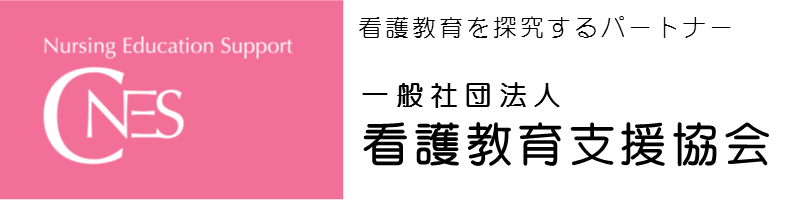何問、できたかよりもまとまりで覚えよう!!
覚えておきたい数字(必修問題)
- 令和5年(2023年)の日本の総人口は、約( 1億2,000万 )人である。
- 日本の令和5年(2023年)における女性の平均寿命は( 14 )年。
- 日本の令和5年(2023年)における男性の平均寿命は( 09 )年。
- 平均寿命は( 0 )歳の平均余命である。
- 令和5年(2023年)の死亡数は約( 157万6,000 )人。
- 日本の令和5年(2023年)における出生数は約( 73万 )人。
- 令和5年(2023年)、年少人口の構成割合は( 4 )%である。
- 令和5年(2023年)、老年人口の構成割合は( 1 )%である。
- 従属人口指数は( 2 )である。従属人口指数は、年少人口と老年人口の合計を生産年齢人口で割ったものに100を乗じたものである。
- 生産年齢人口は( 15~64 )歳までの人口である。
- 令和5年(2023年)の国民生活基礎調査における平均世帯人数は( 23 )人。
- 令和5年(2023年)の調査で高齢者の単独世帯の割合は( 7 )%である。また、夫婦のみの世帯の割合は( 32.0 )%でやや増加している。親と未婚の子のみの世帯の割合は( 20.2 )%である。三世代世帯の割合は( 7.0 )%で、過去10年間で減少している。
- 令和5年(2023年)には65歳以上の者のいる世帯数は全世帯数の( 5 )%。
- 日本の令和5年(2023年)の人口動態統計における悪性新生物(腫瘍)による死亡は3%を占め、死因別順位では第( 1 )位であった。死亡者数は38万2,504人であった。
- 令和5年(2023年)の人口動態統計における主要死因別の死亡率で老衰の順位は( 1 )位。
- 令和5年(2023年)の性・部位別にみた悪性新生物〈腫瘍〉の死亡数では、女性は大腸(結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸)が( 1 )位。
- 15歳から49歳までの女性の年齢別出生率の総和を合計特殊出生率という。令和5年(2023年)は( 20 )であった。
- 令和5年(2023年)の人口動態統計における妻の平均初婚年齢は( 7 )歳。
- 令和5年度(2023年度)の男性の育児休業取得率は( 1 )%であった。女性の育児休業取得率は( 84.1 )%であった。
- 労働基準法では、産前( 6 )週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合の休業、産後( 8 )週間を経過しない女性を就業させてはならないことを規定している。
- 労働基準法では、育児時間として、生後満1歳に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも( 30 )分、その生児を育てるための時間を請求できるとされている。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉における介護休業の取得について、対象家族1人につき3回まで、通算( 93 )日まで休業できる。
- 保健師助産師看護師法の第33条において、業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師は( 2 )年ごとに氏名、住所などを就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられている。
- 令和5年(2023年)平均の労働力人口は総数( 6,925万 )人(男性3,801万人、女性3,124万人)。
- 令和5年(2023年)の人口動態統計における死亡場所で最も多いのは病院で、( 4 )%。次は自宅17%。
- 日本の令和4年(2022年)における傷病別にみた通院者率が男女ともに高血圧が( 1 )位。
- 令和4年(2022年)の国民生活基礎調査による有訴者率(人口千対)は、( 5 )。病気やけが等で自覚症状のある者を有訴者という。有訴者率では男女とも( 1 )位が腰痛症。
- 令和4年(2022年)の「病院報告」による平均在院日数によると、一般病床は( 2 )日であった。介護療養病床が最も長く( 307.8 )日、次いで精神病床が( 276.7 )日となっている。
- 令和5年(2023年)の患者調査における外来受療率(人口10万対)では消化器系の疾患が( 1 )位である。
- 日本人の食事摂取基準(2025年版)では、18歳以上の男性は( 5 )g未満/日、女性は( 6.5 )g未満/日と設定されている。
- 令和4年(2022年)の国民健康・栄養調査において、運動習慣のある女性の割合が最も高いのは( 70 )歳以上である。
- 令和4年(2022年)の国民健康・栄養調査における男性の喫煙習慣者の割合は( 8 )%であった。同調査の女性の喫煙習慣者の割合は( 6.2 )%であった。
- 令和4年(2022年)の50~59歳男性の肥満者の割合は( 1 )%で最も高く、次いで60~69歳、40~49歳となっている。
- ブリンクマン指数は、喫煙年数×( 1 )日の平均喫煙本数で計算される。ブリンクマン指数は( 400 )以上で肺がん危険群、( 600 )以上で肺がん高度危険群とされている。
- 日本人の食事摂取基準(2025年版)の鉄摂取推奨量は、30~49歳女性(月経あり)で( 5 )mg/日である。
- ( 2007 )年にワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定された。
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について( 40 )時間を超えて、労働させてはならない(労働基準法第32条)。
- 医療保険の給付は診察、処置・手術、薬剤・治療材料、食事療養、入院・看護、在宅療養・看護、訪問看護である。自己負担は( 3 )割(未就学児2割、70~75歳未満2~3割、75歳以上1~3割)で、入院の場合は入院時食事療養費のうち標準負担額を負担する。
- 介護保険は( 40 )歳から被保険者となり保険料を支払う。
- 令和3年度(2021年度)の国民医療費は、( 3 )兆円となった。人口1人当たりの国民医療費は( 38万 )円でである。
- 後期高齢者医療制度における被保険者は( 75 )歳以上の者および( 65~74 )歳で一定の障害の状態にあり後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
- 要介護度が最も高い要介護( 5 )で月額36万2,000円程度、最も低い要支援( 1 )で月額5万円程度の支給限度基準額となっている。
- 介護保険の被保険者は65歳以上の者が第( 1 )号被保険者、40歳以上65歳未満の者が第( 2 )号被保険者である。
- 介護保険によって支給される給付は、要支援( 1・2 )の認定者が対象の予防給付、要介護( 1~5 )の認定者が対象の介護給付がある。
- 介護支援専門員は医師・看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士などの所定の資格をもち、その資格の業務に携わった期間が通算( 5 )年以上あること。
- 介護保険法における認定区分は、要介護1~5および要支援1・2の計( 7 )区分がある。
- マズローの欲求階層論で、所属と愛の欲求は上から( 3 )番目の欲求である。
- キューブラ・ロスによる死にゆく人の心理過程で、死ななければならないことへの怒りは第( 2 )段階である。
- フィンクの危機モデルの承認は4段階のうちの( 3 )番目である。
- 全人的苦痛には、( 4 )つの苦痛がある。
- 生活習慣の改善や予防接種は( 一 )次予防にあたる。
- 21番染色体の全長または一部の重複に基づく先天異常症候群がダウン症候群である。
- 人体は肺サーファクタントという物質を産生する機能がある。胎児期には在胎( 34 )週以降にならないと十分にこれを産生できない。
- 日本版デンバー式発達スクリーニング検査で90%の乳児の首がすわるのは( 4 )か月である。
- 低出生体重児は( 2,500 )g未満をいう。
- IgGは分子量が最も小さいため胎盤を通過するため、母体血のIgGは胎児へ供給される。母体からのIgGが消失するうえに自分で産生する能力が低いため出生後一旦、( 3~6 )か月ころに最も減少する。
- 大泉門が閉鎖するのは生後( 1年3か月~1年6か月 )である。脳圧が亢進する異常があると膨隆し、脱水時には陥没する。
- スプーンが持てるようになるのは( 4 )か月ころ。
- 両親の名前を言えるようになるのは( 4 )歳ころ。
- スキップができるようになるのは( 5 )歳ころ。
- 標準的な発育をしている児において体重が出生時の約2倍になるのは( 3 )か月ごろ。約( 3 )倍になるのは1歳ごろ。
- 母親がそばを離れると泣くなどの行動で示されるのが分離不安である。生後( 6か月から3 )歳くらいまでにみられる。
- 第一次反抗期は( 2~3 )歳ころに多く現れる。
- モロー反射は、乳児の頭部を支え、急に下げたり体位を変えたりすると、上肢を広げて抱きつくような動作のことをいい、生後( 3 )か月ころに消失する。
- 手掌把握反射は原始反射で生後( 3 )か月で消失する。
- 生理的体重減少は出生時の体重の( 5~10 )%程度が正常である。生後2~3日くらいから始まり、生後3~5日に最低となり、生後( 1~2 )週間で出生体重に戻る。
- 乳歯は、( 2~3 )歳ころに計( 20 )本がはえそろう。
- 「ワンワン イタ」のような二語文を話すようになるのは( 2 )歳ころである。
- 令和5年(2023年)度の学校保健統計調査によると、幼稚園・小学校で( 1 )位の疾病・異常は裸眼視力の低下である。2位は僅差でう歯である。
- 学童期の正常な脈拍数は( 80~100 )/分ほどである。
- 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別に出した標準体重から求めた肥満度が( 20 )%以上の体重の児童をいう。学童では肥満度20%以上を軽度肥満、30%以上を中等度肥満、50%以上を高度肥満という。
- 下垂体前葉から分泌される黄体形成ホルモン(LH)は、排卵誘発・黄体形成誘発、男性ホルモン生成促進の機能があり、第( 二 )次性徴の発現に関与する。
- 日本人の平均閉経年齢は約( 50 )歳である。
- 体重に占める水分量の割合は新生児期が最も高く( 80 )%で、乳児期70%、幼児期~成人期で( 60 )%となり、老年期にはさらに低下し、( 50~55 )%となる。
- 医療法において、病院とは( 20 )人以上の患者を入院させるための施設を有するものと規定されている。
- 訪問看護ステーションを開設・運営するには労働時間によって常勤換算して( 5 )名以上の看護職員が必要である。
- 卵管膨大部で受精した受精卵は卵割しながら子宮腔へ到達する。受精後( 6〜7 )日ころに着床を開始し、さらに( 4 )日ほどかけて完了する。
- 死産の届出に関する規程では、妊娠満( 12 )週以後の人工妊娠中絶の場合に届け出が必要。
- 母体保護法に基づく厚生労働省事務次官通知において、人工妊娠中絶は妊娠満( 22 )週未満とされている。
- 在胎週数37週0日から41週6日までが正期産となる。分娩予定日は40週0日なので、最終月経の初日を0日として( 40×7=280 )日である。
- 子宮口全開大から胎児娩出までが分娩第( 2 )期である。
- 成人の1日の平均尿量は( 1,000~1,500 )mLである。
- 無尿とは1日の尿量が( 100 )mL未満、乏尿は( 400 )mL未満である。
- 胃液はpH( 1~2 )の強酸性である。
- 血漿と浸透圧が等しい溶液には、( 9 )%生理食塩水と、( 5 )%ブドウ糖液がある。
- 鼻腔入口から咽頭までの長さが約( 10 )cm、咽頭の長さが約( 12 )cm、食道の長さが約( 25 )cmであるため、成人の鼻孔から噴門までの長さは約( 47 )cmとなる。
- 膀胱内容量が( 150~300 )mLを超えると尿意が生じ、( 600~800 )mLになると膀胱壁が過伸展して痛みを感じるようになる。
- 成人の体重に占める体液(水分)のうち最も多いのは細胞内液で( 40 )%、( 20 )%は細胞外液である。
- 健康な成人の1回換気量は約( 500 )mLである。
- 白血球は、多能性幹細胞(造血幹細胞)から分化した際に、顆粒球・リンパ球・単球の3種類に大きく分けられ、顆粒球は( 65 )%を占め、好酸球・好中球・好塩基球に分けられている。
- 赤血球の寿命は( 120 )日である。
- 赤血球数は男性( 430~570 )万/µL、女性( 380~500 )万/µL。
- 貧血の診断基準(WHO)は、Hb量が男性( 13 )g/dL以下、女性( 12 )g/dL以下である。
- 巨赤芽球性貧血は、ビタミンB( 12 )や葉酸の欠乏が原因で起こる貧血である。
- 脳死の判定基準は、心停止はしていないが(心停止したら脳死ではない)自発呼吸は消失している、脳の機能の消失は深昏睡・脳波の平坦化・脳幹反射消失、瞳孔は左右とも( 4 )mm以上で固定である。
- 脳死の判定基準は、①深昏睡、②瞳孔散大、固定の確認、③脳幹反射消失の確認、④平坦脳波の確認(心電図も同時に確認し連続して30分以上かける)、⑤自発呼吸消失の確認、⑥①~⑤までの条件が満たされてから少なくとも( 6 )時間、生後12週~6歳未満の者では( 24 )時間が経過しても変化がないことに該当した場合である。
- 血清カリウムの基準値は( 5~5.0 )mEq/Lと範囲が狭く、高カリウム血症によって致死性の不整脈や心停止のおそれがある。
- 急性心筋梗塞では( 20 )分以上続く胸痛、左肩・左顎などに生じる関連痛が生じる。
- チアノーゼは皮膚に近い毛細血管内において脱酸素化ヘモグロビン(還元ヘモグロビン)が( 5 )g/dL以上になったときに生じる。
- 日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン2019によると、高血圧となるのは収縮期血圧が( 140 )mmHg以上、または拡張期血圧が( 90 )mmHg以上である。
- 心的外傷後ストレス障害(PTSD)は( 1 )か月以上、心的外傷を負うことになった出来事とそれに関連した刺激の回避、意図せず繰り返し出来事が思い起こされる侵入、睡眠や集中が妨げられる過覚醒などの症状が持続する。
- 糖尿病の診断指標は血糖値とHbA1cである。空腹時血糖値( 126 )mg/dL以上・75g経口ブドウ糖負荷試験2時間値200mg/dL以上・随時血糖値 200mg/dL以上のいずれかと、HbA1c ( 5 )%以上の場合に糖尿病と診断する。
- 令和4年(2022年)の感染症発生動向調査による年間の性感染症〈STD〉報告数で性器クラミジア感染症は( 1 )位である。
- メタボリックシンドロームの診断基準でウエスト周囲径は、男性( 85 )cm、女性( 90 )cm以上である。
- 血清アルブミン値(Alb)は栄養状態の指標であり、( 5 )g/dL以下になると低栄養状態のリスクがある。高値になるのは脱水である。
- CA( 19-9 )は消化器癌、膵臓癌などの腫瘍マーカーである。
- インスリン療法を必要とするのは、( 1 )型糖尿病である。
- インスリンは遮光して( 2〜8 )℃で保存する必要がある。
- 血小板製剤には濃厚血小板があり、保存温度は( 20~24 )℃で、水平振盪する必要がある。血漿製剤には新鮮凍結血漿(FFP)があり、( -20 )℃以下で保存する必要がある。
- ジャパン・コーマ・スケール(JCS)で「普通の呼びかけで容易に開眼する」状態は( Ⅱ-10 )である。
- 徒手筋力テストの判定基準は( 6 )段階である。
- 心音では( Ⅰ )音は僧帽弁と三尖弁が閉じる音で、( Ⅱ )音は肺動脈弁と大動脈弁が閉じる音である。
- 直腸温は選択肢のなかでは最も深部体温に近く、腋窩温よりも( 8~1.0 )℃高い。
- 成人の標準規格のマンシェットは( 14 )cmである。マンシェットの下端は肘窩よりも( 2~3 )cm上(中枢側)になるように巻く。マンシェットと腕の間には指が( 1~2 )本入る程度が適切である。
- 成人女性に導尿を行う際のカテーテルの挿入の長さは( 4~6 )cmが適切である。成人男性に導尿を行う際のカテーテルの挿入の長さは( 18~20 )cm。
- 男性に導尿を行う際、カテーテル挿入を開始するときの腹壁に対する挿入角度は( 80~90 )度が適切である。
- 成人のグリセリン浣腸で肛門に挿入するチューブの深さは( 5 )cmが適切。
- ゴム製湯たんぽの耐熱性を考慮して( 60 )℃の湯を使用し、漏れがないかを確認し、カバーをかけて患者の身体から( 10 )cm以上離して使用する。
- 約( 24 )時間の周期で変動し、その周期が光刺激の変化によってリセットされる現象をサーカディアンリズム(概日リズム)という。
- 陰部洗浄の温度は、体温より少し高い( 38~40 )℃。
- 病室は( 100 )ルクスと規定されている。
- 手術室は最も高い照度が求められ( 1,000 )ルクスで、手術野では( 10,000~100,000 )ルクスとされている。
- 外来の廊下は( 200 )ルクスと規定されている。
- 4ナースステーションは( 500 )ルクスとされている。
- 病院の病床と診療所の療養病床の床面積は医療法施行規則により患者1人について( 4 )m2以上と規定されている。またその他の病床では患者1人について個室では( 6.3 )m2以上、多床室では( 4.3 )m2以上と定められている。
- 病室においては、温度は夏季( 25~27 )℃、冬季( 20~22 )℃、湿度は( 50 )%前後が適している。
- 環境基本法に基づく騒音の環境基準では、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域の騒音の基準値は昼間( 50 )dB以下、夜間( 40 )dB以下とされている。
- 乾熱滅菌は乾熱滅菌器を用いて、内部温度を( 150~180 )℃に維持して、多くは( 30 )分以上の時間をかける。
- 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)は、蒸気圧は( 2 )気圧でほぼ( 121 )℃となる。
- ( 三 )類感染症には腸管出血性大腸菌感染症やコレラなどがある。
- ( 四 )類感染症にはマラリアや狂犬病などがある。
- ( 五 )類感染症には後天性免疫不全症候群(AIDS)、インフルエンザ(季節性)、ウイルス性肝炎、梅毒、麻疹などがある。
- 皮下注射の注射針は、( 23~25 )Gを用いる。
- 皮下注射は、皮下脂肪が( 5 )mm以上ある部位に行う。
- 成人用輸液セット1mL当たりの滴下数は( 20 )滴、小児用の輸液セット1mL当たりの滴下数は( 60 )滴である。
- 点滴筒には( 1/3から1/2 )の薬液を満たす。
- 成人の採血の場合、( 21 )Gあるいは( 22 )Gが向いている。
- 成人の採血の場合、採血部位より( 7~10 )cm中枢に駆血帯を巻く。駆血帯を巻いている時間は( 1 )分以内とする。通常、抜針後( 5 )分間程度穿刺部位を圧迫する
- 皮膚への刺入角度は皮内注射で( 0 )度、皮下注射で( 10~30 )度、筋肉内注射で( 45~90 )度である。
- 坐薬を肛門に挿入した場合、( 1~2 )分肛門を押さえる。
- 坐薬は肛門から( 3~5 )cmの位置に挿入する。
- 1回の気管内吸引時間は( 15 )秒以内。成人患者の気管内の一時的吸引における吸引圧は( -150~-200 )mmHg。6kPa=200mmHg
- 室内空気下での呼吸で成人の一般的な酸素療法の適応の基準は、動脈血酸素分圧〈PaO2〉=( 60 )Torr未満。動脈血酸素分圧(PaO2)60Torr未満は呼吸不全の指標となる。
- 胸骨圧迫は( 一 )次救命処置である。気管挿管は医療器具を用いる( 二 )次救命処置である。
- 成人への胸骨圧迫は、約( 5 )cmで( 6 )cmを超えないように行うのが適切である。また、成人で( 100~120 )回/分のペースで、胸骨圧迫と人工呼吸を合わせて行う場合には( 30:2 )の比で行う。
- ステージ( Ⅲ )は皮下組織にまで及ぶ全層組織欠損である。