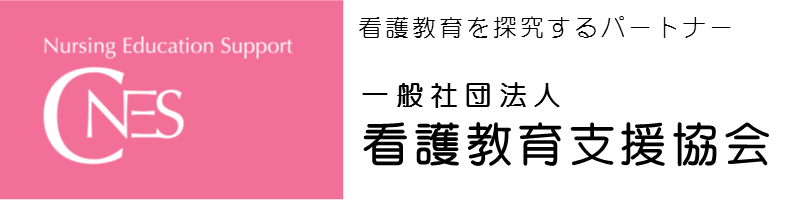「安心」の従来のイメージ(一般的な解釈)に振り回されてはいけない!
- 危険や問題がない、平穏な状態。
- 変化がなく安定した状況。
しかし、この解釈は、外的要因に依存しすぎている。実際の社会生活や人生経験では限界がある。実際には、私たちは常に変化のある世界に生きており、何も起こらない状態を完全に保つことは現実的ではない。
「安心」の定義(能動的解釈)
「安心」とは、『何も起こらない』ことではなく、『何かが起きても、それを乗り越えられると信じることができる』という心理的な強さや自己効力感を伴う状態のこと。
つまり、安心の本質は以下のように整理できる。
- 自己効力感(Self-efficacy):自分には問題を乗り越える力がある、という確信。
- レジリエンス(Resilience):困難な状況や変化に対し、柔軟に適応し立ち直れる能力や心のあり方。
- 信頼感(Trust):自分自身や周囲の人々、社会的なシステムを信じることができる状態。
看護やケア職における具体例で考える
例えば、キャンプナース®や災害時の医療・ケアを想定すると、
「安心」は、参加者が怪我や体調不良にならないことではなく、万一何かあっても適切な知識・技術・サポート体制を持った看護師や主催者たちがすぐに対応できるという信頼感や、参加者自身が困難を乗り越える力を育てること。
そのため、キャンプナース®の研修や地域ケアにおいては、「問題がゼロの状況を目指す」のではなく、「何が起きても対応できる能力や信頼関係を築く」ことが安心感の核心になる。