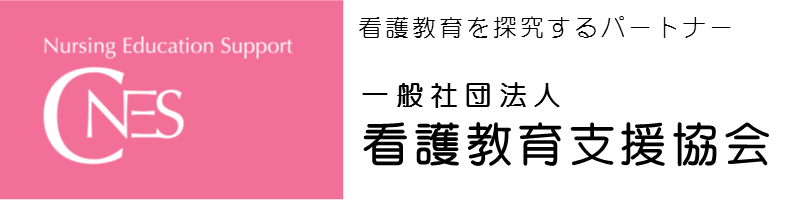「あの時、死ななくてよかった」
私の家庭は、父がろくでもない人だったということと、母がその父と愚痴を垂れ流しながら半世紀ほどを共に過ごしたこと以外は、特記事項はない。どこにでもある家庭のように思う。しかし、私はかなり個性的な人物に育っていると自覚している。協調性は果てしない努力と根性を必要とするが、それも「個性だ」と笑って許してくれる友だちや、「個性的だ」とあきらめている主人や息子、お義母さんにも見捨てられずにいる。
私ばかりでなく誰でも、何時、身体や精神を病んでもおかしくない。また、社会的に孤立することがあってもおかしくない。私は、運良く、今日も朝ごはんを食べ、仕事をしている。十分ラッキーな人である。
そんなことをふっと思ったのは、患者さん(Aさん)を思い出したからだ。Aさんは、当時30歳代半ばだった。私と同世代だった。Aさんは軽度のうつ病だった。その時出会ったのは、うつ病の治療ではなかった。うつ病のために自殺を企てたことが原因で膝から下を切断する治療と、ほかの骨折の治療とリハビリが目的の入院だった。
Aさんと私はよく似ていた。気分屋なところ、感情のコントロールができないところ、その反面自分でちゃんとやりたいところ、母と距離を置いた方が精神的に安定するところ、何でも匂いをかぐところ・・・・・。
はじめはAさんが私に言った。痛み止めの筋肉注射を打っているときだった。「ウチら、よう似てるな~」と。「確かに」と思った。
「ウチな、児玉さん見ていて、なんかわかった気がする。うちのアカンとこ」。まさかディスられるとは思わなかったが、とても興味深かった。「一回出してしまった言葉は、引っ込みがつかんから気を付ける。ずっと気になることをためておくと、何かのきっかけで今それを言わなくてもいいことまで言ってしまうやろ、それはあかんわって思った。」「あるある。」腋窩に大量の汗が出てくる感じがした。
「ほかにな、自分一人でやらんでもええなと思った。後輩も仲間もおるから、みんなにやってもらってもいいと思った。自分は一生懸命やってると思ったらあかんわ。イライラするだけやん。」「なるほど。」だんだん逃げたくなってきた。
「退院したら、母親とはもう別に住むわ。ダンナともちゃんと離婚する。子どもらと母子寮みたいなところに住んで、仕事探すわ。」「ほう~。いろいろ決断したんですね~」「児玉さんみてたら、分かったわ。」「アカンところでしょ~」「そうそう」と言って二人で大笑いした。痛み止めの筋肉注射を打つよりも効果があったかのように笑った。
私の何を見て、そこまでAさんを決断させたものは何かは定かではないが、褒められたような貶されたような微妙な後味を残したが、おっしゃる通りだと思った。
Aさんとは、退院して2年ほどたってから、外来の廊下で再会した。「児玉さん!」と声をかけられたが、だれかわからずに「こんにちは~」と挨拶をした。「ウチやで!」と言ってロングスカートの裾をふわっと持ち上げると、片方が義足だった。「Aさん!だれかわかりませんでした!」「元気?」「はい元気です」もはやどっちが看護師かわからない。「それならいいけど」。「Aさんこそ、お元気ですか?」「ウチは元気やん。資格も取って、子どもらと楽しく暮らしてるで~」その表情や声のトーン、カラフルなファッションから本当に楽しく暮らしていると感じた。別れ際に「ウチな、もう泣けへんって決めてん。生きててよかったわって、もっとかっこよくなってから、もっとかっこよく言う人になりたいと思うねん」と言った。その言葉を聴いて、私は鼻の奥がキューンとなるくらい目頭が熱くなった。その私の顔を見て、Aさんが泣きそうになっていた。「泣いてますやん」と突っ込みを入れておいた。相変わらず大笑いした。
「あの時、死ななくてよかった」と思えるような看護。自分のまま生きていることを大事にする看護のことなのだろうか。
「あの時、死ななくてよかった」と思える看護をしたいと思った。

「看護」とは何かについて考えていくことを意図として、「看護師日記」を書くことにしました。私の看護師、看護教育の経験に基づいて表現していますが、人物が特定されないように、また文脈を損なわないように修正しています。