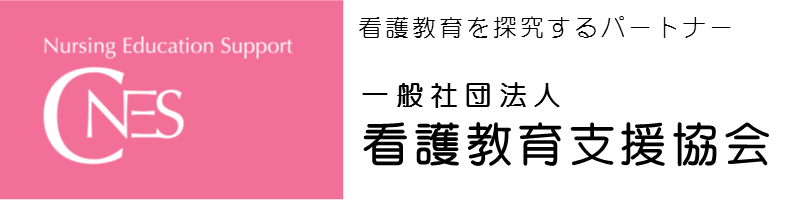看護学生時代の実習の思い出
私が看護学生の頃は、手術室の実習があった。30年以上前の前の話だ。
印象に残っているのは、糖尿病足病変のために壊疽となり、足を切断する手術の外回り看護師の実習をしたことだった。先生の名前も顔も思い出さないのだが、糖尿病について、足病変について、ほかに同じような治療を必要とする末梢動脈疾患について質問された。私は、床に落ちた血液のついたガーゼを拾い集める手を止めて、考えながら答えていると、「手を止めないで、答えなさい」と言われた。「んなら、質問するな」と思った。苛立ちと骨の焼けこげるニオイが、痛みを感じていた。
「学生さん、そこのバケツ持ってきて」と先生に頼まれた。「はい」と言って、先生の近くまでバケツを持って行った。コーナンに売っているようなバケツにビニール袋が入れられていた。「思っているより、重たいで」と先生が言った。片手には、膝から下の切断した足を持っていた。私は、このバケツに足を入れるのだと悟った。そして、重たいのだと覚悟して「はい」と言った。先生は、私の持つバケツに足を入れた。確かに重たかった。振り返って、外回り看護師さんの顔を見ると、切断した足をどう取り扱うかを説明してくれたので言うとおりにした。先生は、また術野に向かいながら「看護師さんになろうと思う人は、足を渡されても平気なんやな~」と言うと、器械出し看護師さんが「あの子たちは新人類だから、ちょっと私たちとは感覚が違うのよ」と言った。今も昔も変わらないジェネレーションギャップである。
なるほど。私は切断した足を受け取った時点で、気分が悪くなって倒れたり、泣き出したりするのが正解だったのか、と考えた。
実際のところ、私は、その時の切断された足がどんな感じだったのか、思い出せない。ただただ、自分が生き延びるために、すべての感覚を停止させ、黙々と実習をしていた。そこに余分な感情も、患者さんのヒストリーも取り込まないようにしていた。一瞬でもそんなことをしたら、嘔吐してしまう。思考停止した爬虫類のように、じっと時が過ぎるのを待つだけの人間になっていた。
実習が終わり、寮に戻ると、その日の晩ごはんは、鶏の照り焼きだった。鶏の皮を眺めながら、いろいろ考えそうになった。しかし、糖尿病足病変のために壊疽となり、患者さんの生命を守るために切断した足と、私の命をつなぐために犠牲になった鶏は何の因果関係もない。「いただきます」といって鶏肉を食べた。お皿を洗う流し台には鏡があった。鏡に映し出された私は、一日中、サージカルキャップをかぶって実習していたので、海苔弁当の海苔がめくれあがったのような前髪になって写っていた。ため息が出た。ため息しか出なかった。
その日の夜だった。寮に病院から電話があった。「解剖があるから、該当者は白衣に着替えて、解剖室に来なさい」と言う主旨だった。今の時代では考えられないが、私の通う看護学校の3年生は、突然、解剖見学があった。「該当者って、私やん」。私を含む4人が、慌てて白衣に着替えて病院に行った。寮と病院はわずか5mほどだったので、更衣室は寮の1階にあった。足の切断の次は解剖か・・・。
解剖は、多臓器にがんが転移した女性だった。とても痩せていたが、60歳になっていない。今の私と同じくらいの年齢だと思う。見覚えのある先生が二人と、あと一人、とても若い男性が一人いた。医学部の学生さんだった。夜の病院、地下の解剖室は床からシンシンと冷えた。そしてホルマリンのニオイに包まれていた。目や耳からに入ってくる情報は、いっさい頭に入っていかなかった。
先生たちは会話の中で、医学部の学生さんに対し「お母さんの黄疸は・・・・」という言葉が出できたのでひっかかった。なぜ、お母さんと呼ぶのか不思議だった。途中で、先生が「あ、看護学生さんたちに言ってなかったね。Aさん(遺体)の息子さんが医学部の学生なので、一緒に学んでるんだよ」と言った。のけ反った。
医学生は、先生の話を聴きながら、母親の臓器を切り取っていた。そして何やら質問をしていた。私たちは、教科書で学んだものとはかけ離れた血の通っていない臓器、しかもがん細胞だらけの臓器を見学して、その時間を終えた。
私たちは、医学部の学生さんに挨拶に行った。彼は、マスクとサージカルキャップをはずして、私たちに頭を下げてくれた。彼が顔をあげたとき、涙と鼻水でぐしゃぐしゃになっていた。私たちも泣いた。5人でおいおい泣いた。私たちは、とうとう何の言葉もでてこず寮に戻った。
この日、この場面がなかったら、私は切断した足を持っても何も感じようとせず、晩ごはんに鶏肉を食べて、ただ生きているだけの人間になるところだった。自分として、感じたことを生かし、言葉や態度で表現しなければ「看護」にならないと思った出来事だった。