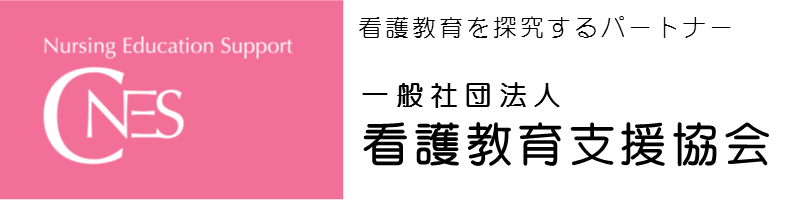つつましやかに、自分の席に着く
私は看護教員をしていたということもあって、卒業生から結婚式に招待されることがある。卒業生も気を使ってくれて、今の上司の席ではなく、同じ学年のお友達の席に私を座らせてくれる。だから、その席はプチ同窓会になる。どの結婚式もとても感慨深いものがある。
いろいろなことを乗り越えできた結婚式もあった。
卒業生のAさんは、お母さんと二人暮らしだった。お父さんは幼いころに亡くなったらしい。Aさんのお母さんは、Aさんが看護学校を卒業して働き始めたころ精神疾患を患った。診断名がいまいちよくわからなかった。私は精神科で働いていた経験があるという理由で、お母さんのことは相談にのっていた。しかし、いよいよ、自分のことができなくなり、Aさんも仕事どころではなくなった。その時、お付き合いしていた彼も、お母さんのセルフケアのお世話をしてくれていたらしい。
しかし「もう、無理です。」と言う日が来た。お母さんも精神病院に入院することになった。診断名は統合失調症。なかなか合う薬が見つからず、よくなったり悪くなったりを繰り返した。
Aさんも彼も疲れ果てていた。Aさんは、卒業してから勤めていた病院をやめて近所のクリニックで働き始めた。彼もお母さんが外泊や退院しているときは、一緒に介護してくれていたようだ。彼は、医療従事者でも福祉関係の仕事でもない。にもかかわらず、陽性症状バリバリの統合失調症のケアができるというのはすごいな、と感じていた。
二人は結婚することになった。
Aさんのお母さんは入院中だったが、娘の結婚式と言うことで外泊できることになった。私とお母さんは、看護学校時代からの知り合いなので、「お母さん、おめでとうございます」と声をかけると下を向いて涙ぐんでいた。留めそでを着たお母さん。人がいっぱいの結婚式場。ストレスにならないか心配になった。私は、同窓会テーブルから飛び出して、Aさんのお母さん担当看護師として今日を乗り越えたいとさえ思った。
でも、その傲慢な考えは、あっけなく木端微塵となった。Aさんとお母さんは、バージンロードを颯爽と歩いてきた。颯爽というのは、大袈裟だった。薬の副作用だろうか、パーキンソン様の症状が出ていたので一歩一歩だ。にこやかな花嫁に対して、仮面様顔貌と振戦のあるお母さん。ますます応援したくなった。
結婚式場に国籍が明らかに違う人が何人かいる。どうやら、彼の姉妹が国際結婚をしているらしい。ご主人は、肌の色が黒く大きな体の人だった。子どもたちもみんな黒くチリチリの髪をお団子にしてもらってリボンをつけていて可愛い。さらにそのご主人は、プロのゴスペルシンガーだった。披露宴の途中で歌ってくれて、吹っ飛ばされるほどの声量に鳥肌が立つ、そして涙が勝手に出てくる、完全に自律神経系がおかしくなっていた。
本当に大きなお世話だが、国際結婚を認める、お嫁さんのお母さんが精神科から外泊をしてきて結婚式に出席するを認める・・・彼のお母さんとはどんな人物なのか、気になった。私は、汗のかいたビール瓶をもって彼のお母さんに会いに行こうと立ち上がった。すると家族席で、彼のお母さんは、Aさんのお母さんの肩を抱いていた。留めそでを着たおばちゃん二人が肩を寄せ合っている光景もなかなか見ることのない絵である。しばらくその絵を呆然と眺めていた。
私の出番はなかった。彼のお母さんは、肌の色が違っても、どんな病気を持っていても「関係ない」という人だった。「関係ある」のは私だった。今、Aさんのお母さんがしんどくなったから、そっと肩を抱いている。そこにエビデンスも経験もいらなかった。必要なのは自分の在り方と行動力のみ。私がAさんのお母さん担当看護師をしようなんて考えたこと自体が恥ずかしかった。傲慢の何物でもなかった。
この披露宴は、いろんな場所で生まれ、育ち、一人一人が生きてきた歴史を認め合って成り立っている場なのだ。二人だけが祝福されているのではないと思った。集まった人たちみんなが、祝福されているように感じた。本当に、この場にいることができたことに感謝した。そして癒された。そして、つつましやかに自分の席に着き、披露宴を楽しむことにした。
忘れることのできない披露宴だった。

「看護」とは何かについて考えていくことを意図として、「看護師日記」を書くことにしました。私の看護師、看護教育の経験に基づいて表現していますが、人物が特定されないように、また文脈を損なわないように修正しています。