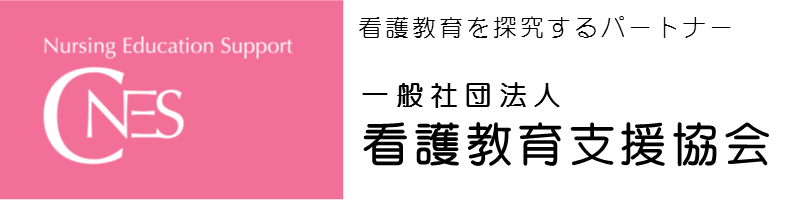忘れられない実習
私には、忘れられない実習がいくつかある。中でも印象に残っているのは、精神看護学実習である。私の実習先は、男子閉鎖病棟だった。30年以上前の話なので、精神科看護の歴史の1ページに刻まれるような古の精神科看護と言ってもよい。
私が印象に残っている患者さんは3人いる。いずれも受け持ち患者さんの話ではない。
新しい人の顔を見ると生年月日を尋ねるという患者さん。私も突然、「誕生日いつ?」ときかれた。「7月生まれです」と答えると、西暦からちゃんと教えてと言われた。西暦からちゃんと答えると、指を折ってぶつぶつと数えて、「日曜日!」と言って立ち去って行った。私の誕生日は、日曜日だったのか!知らなかった。指導看護師さんが「ほんまかな~と思うけど、いつも正確なんよ。」と教えてくれた。さらに指導看護師さんは興味深いことを言った。「指で数えてるみたいな時間あるやろ。あれは、実は数えているんじゃなくて、カレンダーを思い出しているんだと思う。」「そ、そうなんですか!」。のちにサヴァン症候群という症状を学び、真っ先にこの患者さんを思い出した。
印象に残っている二人目の患者さん。その病院には中庭があって、みんなで散歩に行く時間があった。その患者さんは、大量のハトを呼び寄せることができた。餌を巻いているわけではなく、空に向かって何かを言うと大量のハトが集まってくるのだ。毎日集めることができた。付き添っている看護師さんたちは、いつもの光景なのでハトが来たな~と思っているのかもしれないが、初めて見た私にとっては衝撃である。その患者さんは、ハトに名前を付けているようだった。その光景はハトと対話をしているようだった。その時、私は「聴き耳頭巾」の民話は実話だったと確信した。
三人目の患者さん。作業療法の時間、みんなでちぎり絵を作っていた。私も一緒にちぎり絵を作るのに参加していた。ところがある患者さんのちぎり絵だけは、作業療法のレベルをはるかに超えていた。夢中になってちぎり絵に没頭している後ろ姿は、山下清の世界観だった。下書きはない。隅の方からじりじりと仕上げていくのだ。この患者さんと山下清画伯の違いは何か、真剣に考えた。一つの作品に時間がかかるので、私の実習期間で完成品を見ることはできなかったが、過去の作品を見せてもらった。横にしてみたらよいのか、縦にしてみたらよいのか、よくわからないと言えばよくわからないが、芸術作品であることに違いはなかった。圧巻だった。私は「素晴らしい作品ですね」と声をかけた。しかし、患者さんが集中しているときは雑音でしかなかった。何の興味も示さなかった。
それぞれみんな精神分裂病(現在は統合失調症)と診断されていた。
今の時代だったら、入院じゃなくて、別な形で注目を浴びていてもおかしくない。違う世界を生きている人たちだと思った。とはいえ、当時の日本でいえば「入院」を否定していない。30年以上前の日本バブル時代、これらの特殊な能力を生かしながら生きていくためには環境が整っていなかった。
しかし、時代は変わっていく。治療方法も変わっていく。そして、社会から求められる能力も変化する。白装束が黒い喪服に変化するほどの変化が訪れるかもしれない。
ただ、その時代に応じてどんなに突出した能力があっても、社会の中で生かされるか、社会の中で悪用されるか、社会の中で生かされずにその他大勢と違うという理由で自尊心を傷つけられるか、次世代で開花するかは謎である。
やっぱりここでも「看護」の目が大事なのだ。
看護の目とは何か、常に他者を可能態としてみる力のことだ。

「看護」とは何かについて考えていくことを意図として、「看護師日記」を書くことにしました。私の看護師、看護教育の経験に基づいて表現していますが、人物が特定されないように、また文脈を損なわないように修正しています。