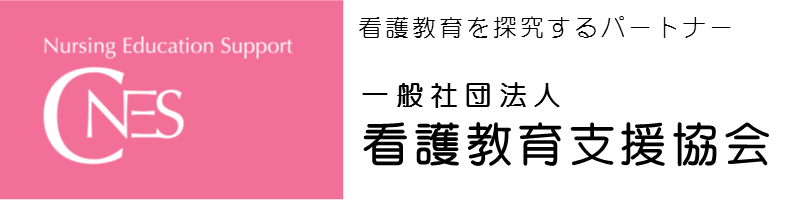介護からの解放
父は、自宅のベッドで、母と私の腕の中で息を引き取った。
死ぬ瞬間、カッと目を見開いて、私と母を凝然として見た。大きな呼吸をしているかと思えば、突然、その息は止まった。母が「お父さん!お父さん!」と呼ぶので、私は母に手を当てて制止した。もう、父は「行く」と決めたのだから「行ってらっしゃい!」でいい。
父と過ごした時間は、母にとっても私たち兄妹にとっても決して美談ではなかったのだから。
父はろくでもない父だった。お酒を吞んでは管を巻き、暴力をふるうこともあった。私の結納や結婚式でさえも出席しなかった。兄が代役を務めてくれた。「生まれ変わったら私の父にだけはなるな」ときっぱりと言っておきたい。
父が死んだあとは、訪問診療の医師に死亡確認をしてもらった。そのあとは、孫たちと一緒にシャンプーをしたり、全身を拭いたり、死化粧をしたりした。母がどうしても着せたいという着古した丹前を着せた。悔しいが似合っていた。お酒を呑んで管を巻いている父を思い出すほど父だった。蹴っ飛ばしてやりたいくらいの思い出がよみがえってきた。しかし、孫たちがおいおいと泣きながら、父の死後のケアをしているので、私一人が父の遺体を蹴っ飛ばすわけにはいかなかった。私は先輩看護師のように孫たちに死後のケアを教えていた。一粒の涙も出なかった。
兄は、粛々と葬儀の準備を始めていた。兄は「よしこ、明日は夏祭りで花火大会があるから、葬式の日をずらした方がいいらしいわ」と申し訳なさそうに言った。とことん迷惑な父であった。「仕方ないねえ」としか言いようがない。父の遺体は仏壇のある部屋に移され、母や兄夫婦、孫たちに囲まれ二夜を過ごした。私は別の部屋で寝た。
父の向こうの窓には、大輪の花火の明かりと少し遅れた振動が伝わってくる。「最後にこれが見たかったのか・・・・」。私は、ことごとく父のわがままに付き合わされている気分になった。
そういえば、私が小学生のとき「花火」という作文を書いたことがあった。唯一父に褒められた作文だった。有田川に写った花火がきれいだったという描写がいいと言っていた。その時は「どうせ機嫌良くほめているのだろう」と冷然たる態度で聞いていた。
またこうして、父と花火を見るとは思わなかった。
何度も何度も打ち上げられる花火と一番静かな父と、縁側に腰掛ける子どもたちを見ながら、介護からの解放を感じた。