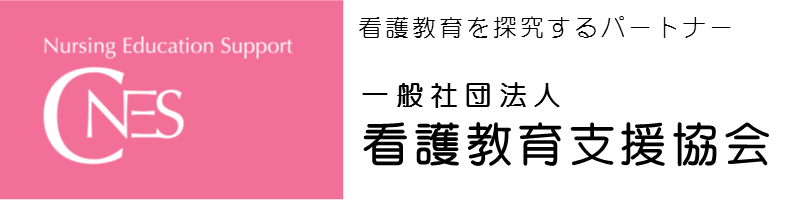断捨離
江藤は住み慣れた大阪の下町から滋賀県の生まれ育った家に引っ越しをした。実家の家は、所狭しとモノが置かれていた。一人暮らしだった年老いた母が、大きな家電や家具を廃棄したりすることは誰かの助けが必要だ。モノが増え続けるのも納得ができる。長押(なげし)には、曾祖父母や祖父母の写真に加えて、江藤の小学校や中学校時代の作文コンクール賞状や水泳大会の賞状なども当時のまま飾られていた。祖父に至っては戦死しているのでやたらと若いのでいつ見ても苦笑する。
江藤が地元の高校を卒業して大阪に出てから、この実家の空間は時間が止まってしまったのだろうかと思った。トイレやお風呂はリフォームしたと言っていたがほかは手付かずだ。大きな段差、建付けの悪いふすま、黄ばんだ障子、埃だらけの欄間、時間が止まっているように感じたが、妹が結婚を機に家を出て以来、夫婦が二人で淡々と時間を重ねてきた空間でもあった。
「よし、全部、捨てよう」。江藤は声に出して言った。時間は有り余るほどある。黙々と片付けを始めた。久しぶりに「やる気」に満ち溢れている自分に気づいた。
残暑厳しい8月の下旬。江藤は受診のために大阪に来た。A病院の外来にほとんど人の気配がない。江藤が病院に入った瞬間に登録されている診察アプリが作動してスマホに行先が案内される。採尿をしてから内分泌代謝科に行けばいいらしい。ホテルマンのような男性が一人、不慣れな人の対応のために立っている。しかし、そのような障害を持っている人が来院した時点で、必要なスタッフが動くので外来は静かなものだ。江藤の後に入ってきた電動車椅子の高齢の女性が入ってきたときには、15秒ほどで看護師がやってきて「こんにちは。暑い中お疲れさまでした。地下鉄は・・・・」と話しかけていた。
江藤も採尿をしようと廊下を歩いていると「江藤さん、こんにちは!」と声をかけられた。杏奈だ。江藤は豆鉄砲を食らった顔をしながら「ああ新堂さん、お久しぶり」と言った。江藤も自然と笑顔になった。「僕が外来の日も予約時間もわかるんだね」「はい」と言って笑った。「江藤さん、今日は診察の後、少しお話しませんか。お時間ありますか。」「はい、診察が終わったら連絡すればいいかな。」「診察が終わったらこちらで分かりますので、また玄関のラウンジで待っています。」「便利ですね。お忙しいのにすみません。」「病院のAI化は、より価値のある仕事ができるために進んでいるんですよ。看護師が患者さんとお話しできないほど忙しいなんてことはありません」と言ってほほ笑んだ。
江藤の主治医は40歳くらいの女性の野々村先生だ。「血糖値も安定していますね。お母様のことやお引越しされることを聴いていたので、無理されないか心配しましたけど大丈夫そうですね。」「はい。」「毎日暑いですが脱水にも気を付けてくださっているようですね。腎臓も頑張って働いてくれていますね」言った。江藤は「いやいや、病気になる前にやっとけばよかったのですが」と自嘲気味に笑って下を向いた。野々村は静かに首を振って「失ってから有難さが分かることもあります。お気づきになられて嬉しいです」と言った。
「滋賀県からわざわざお越しいただいたにもかかわらず、私からは何も言うことがありません。いつものお薬を出しておきます。ほかに何かお困りのことなどありますか」「いえ、とくに何もないです」「そうですか、細かなことは新堂さんにお伝えくださいね」と野々村は言った。江藤は「あ、」という顔をした。新堂とこの後ラウンジで話をすることを知っているのかと思うと気まずい気持ちになったからだ。野々村は透かさず「知ってますよ。私たちはワンチームで江藤さんの健康を支えているのですから」と言って笑った。「でも安心してくださいね。治療に不要な情報はカルテには残りません。安心していろいろお話してください。対話はいいですよ。とくに年代の違う人との対話は視座を変えてくれますからね。楽しんでくださいね。楽しむことも健康維持には欠かせません」といって笑った。
野々村は、一切、パソコンやタブレットに目を向けない。音声でカルテに入力されているらしい。医療秘書の男性がカルテに誤記入がないかをチェックしている様子で何も操作していない。きっとこの後、野々村が再確認するのだろうと江藤は思いながら診察室の中を客観視していた。江藤は大学を卒業し大手家電メーカーに就職したときは、病院を相手にする営業をしていたので、医者や事務の言動のみならず導入しているAI搭載のカルテなどに興味があった。
短い時間の診察だったが、江藤は先生に褒められた小学生の子どものように明るい気分になって玄関のラウンジに向かった。杏奈も向こうからやってきて「江藤さん!こっちです」と手をあげた。江藤は「全く無駄がないな」とつぶやきながら鼻で息を吐いた。
ラウンジで江藤と杏奈は45度の位置で腰を掛けた。杏奈は「江藤さん、お母様のことご愁傷さまでした」と言って頭を下げた。「どうも」と言って江藤も頭を下げた。「いろいろ落ち着かれましたか?」「うん落ち着いたというより、せわしなく動いていると言った感じかな。」「え?」と杏奈は目を丸くした。「実家に引越しをしてみると、半世紀分の不要なものであふれかえっていて、断捨離をするのに一生懸命なんだよ。まだ同級生にも会えていないんだ」と言った江藤の顔は、以前より若々しく見えた。
杏奈は意外なことを口にした。「半世紀、不要なものにあふれかえるお家って平和の象徴ですね。」「ん?」「私の実家は、平成23年紀伊半島大水害ですべて流されてしまったんですよ。でも、その時は父と一緒に避難していたので命まで奪われなかったのですけどね。思い出のモノは一つもないですよ。母の思い出も・・・」と言って寂しそうに笑った。江藤は返す言葉もなかった。その様子を見て杏奈が「あ、でもねラッキーなことに親戚の家が空き家になってるからと言って、同じ村の中でも比較的被害が少なかったところに引っ越すことができたんです。そこが私の実家になったんです。その年は東北の震災もあった年だから、避難所生活の人も大勢いる中で私は恵まれていると思ったんです。村だったのでみんなで助け合ってね・・・」と言って笑顔で目を合わせた。江藤は「新堂さんは、若いのにいろいろと経験をしているんだね」と言った。杏奈はごく普通のトーンで「別に望んで手に入れたものじゃないけど、いろんな経験は生活していくうえで役に立っていると思っています」と言った。
杏奈は「私のことより、この前いただいた江藤さんのお手紙、何かすごく前向きな感じがしましたよ。何かあったんですか」と話を切り替えた。江藤は、杏奈の話を聴いた後に自分の平凡な日常を語ってもいいものかと少し思案した。杏奈は思案している江藤を見て「心を動かす出来事に、大きいとか小さいとか関係ないですよ。それに人と比較する必要もありませんよ」ときっぱりと言った。江藤は、話そうとしている言葉が前歯の裏まで出かかっている感覚があった。
続く・・・・
これはフィクションです。実在の人物や団体などとは実在しません。
https://kango-support.or.jp/nurse-diary