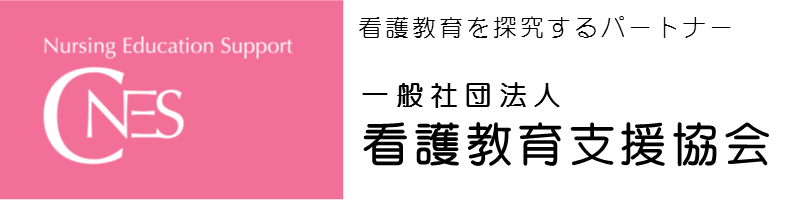天使になって
Aさん、60歳の男性。肺がんが見つかったときには、すでに食道や脳への転移があった。「1本もタバコを吸ったことがない人なのに」と奥さんは肩を落としていた。Aさんは放射線治療を受けていたが、途中で症状を緩和するだけの治療を望んだ。
そこに至るまで、セカンドオピニオンを受けたり、自分の病気について熱心に調べている人だった。子どもたちもお父さんのことが大好きで、インフォームドコンセント受けた時に肩を寄せ合って静かに泣いていた。
そして、Aさんは絵にかいたような温厚な性格だった。自分の病気や症状についても「しょうがないよ」と言ったきり、愚痴も泣き言も一切言わなかった。一方、奥さんは「水虫ができているようだ」と言って、スタッフステーションに慌てて報告に来たりしていたが無理もなかった。夫婦で、死を受容する過程でお互いが何を話し、どんなふうに時間を過ごせばいいのかわからない。そんなものだと思う。看護師が仲介に入ることもある。思い出話を聴いたりすることもある。でも本当は、二人でないとわからないことの方がはるかに多い。
Aさんは、絵を描いている芸術家だった。個展も開いていたようだ。放射線治療が始まるまでは、独特の長髪で奥さんがいつもカットしていたらしい。白髪がない黒髪で、髪の量も少なくなかった。だから、赤塚不二夫に登場するキャラクターのような印象だった。芸術家なので、かえってカッコよく見えた。別の仕事だったら、間違いなく「シェーおじさん」と言われていた。肩書で人間がコロっと騙されるのも納得できる。
放射線治療が始まる前に、40年ぶりに短髪にした。「戦争に行く前のおやじだな」と頭をなぜながら笑っていたが、目の奥は寂しそうだった。長年やってきたこと、トレードマークを変えなければならない心境を理解しようとするだけで、喉に何か閊えるものを感じる。苦しさ、寂しさが伝わってくるからだ。
Aさんの作品は、絵ハガキになっているものを見せてもらったことがある。温厚なAさんが描いた作品のイメージとはちょっと違っていた。荒々しいわけではないが、繊細さの中にも力強さがあり、人物画に登場する印象深い瞳は、誰をモチーフにしているかわからなかった。少なくとも面会に来る家族の中にそんな目の人は一人もいなかった。でもそれは、ただの姿かたちであって、Aさんか奥さんのどちらかの元来の目は、違っていたのかもしれない。
放射線治療を受ける前に短髪にした髪の毛は、あっという間に真っ白になった。さらに痩せていった。白髪と同じほど、白い顔になっていった。
それでも毎日、Aさんはスケッチブックに向き合っていた。面会や巡回のない時間帯を見計らって描いていた。タイタニック号が沈んでいくとき最後まで演奏をし続けた音楽家と重なり合う感じがした。「主よ御許に近づかん(Nearer, My God, to Thee)」という賛美歌だ。使命は人を強くすると思った。私たちも「見せてください」とか言わずに創作活動を見守ることにした。
どんな絵を描いていたのか、結局のところ私たちは知らないまま亡くなってしまった。
無心になる時間をつくっていたのか、遺作として残したかったのか、いろいろ考えられると思う。しかし、Aさんの場合は、心を空っぽにする時間を作っていたのだと思う。自ら、その時間をつくりだすことのできる人間の持っているエネルギーには敬意さえ感じる。あれこれ考え始めると、いろいろ心配なことばかり。考えても無駄なのは百も承知。Aさんは、そんな時にこそできることを知っていて、使いこなせる人だった。それを芸術と言うのかもしれない。
のちにAさんの作品について、奥さんから聞く機会があった。泣いたり、落ち込んだり、叫んだり、怒ったりしている自分の姿を描いていたそうだ。そして天使になって、家族の姿を見下ろしている姿が最後の作品だったそうだ。奥さんは「いつもそばにいてくれる気がする」と言っていた。夏になって、風鈴がなると、Aさんが通ったと感じると言っていた。そういうものなのかもしれないと思った。
Aさんは、無心にスケッチブックに向き合いながらも、残される家族に「自分が死んだ後も、いつまでも泣いていないで」というメッセージを残してくれていたのだと思った。
無心になりながらも、他者を思いやる時間、その時間は自分の中の執着から解放される。

「看護」とは何かについて考えていくことを意図として、「看護師日記」を書くことにしました。私の看護師、看護教育の経験に基づいて表現していますが、人物が特定されないように、また文脈を損なわないように修正しています。