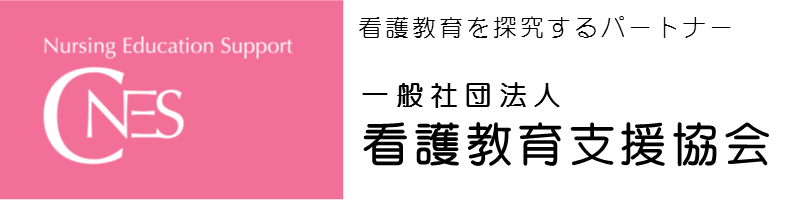オンラインカンファレンス実践報告
昨日、第2回目のオンラインカンファレンスが終わった。テーマ「死生観を問い続けること」。
30年前の事例を掘り起こしてきてもらった。
患者のAさんは、30代男性で会社員だった。病名は、腹膜偽粘液腫。手術によって、大量の腹水と多量の粘液腫を摘出した。術後温熱療法(低分子デキストラン)+抗癌剤(シスプラチン)投与を複数回施行した。何度も腸閉塞も合併したが、何度も癒着剥離や腸管切除術施行した。それでも「僕は生きたい」と意思表明した。
結婚したばかりのお嫁さんがいた。お嫁さんはだんだん病室に来ることができなくなった。
彼は、孤独だった。自分の病気のこと、治療方針のこと、詳しく理解していた。そのことがかえって訪室する看護師の細かなミスの指摘をするようになり、治療方針をめぐって語気を荒げることになった。また「僕はいつ死ぬんですか」と言う質問をするようになり、看護師の足が遠のいてしまった。にもかかわらず、Aさんのナースコールは頻回になった。訪室してスタッフステーションに戻る途中で彼のナースコールが再びなる。当時の疲弊したAさんと看護師たちの心境を語ってくれた。
今の自分なら、何ができるだろうか。事例提供者は当時入職したての看護師だった。今なら、もっとそばにいること、一緒に人生を振り返ることができると思う。語気をあらげられることがあっても、「生きたい」と叶うことのない感情の行き場を怒りで表現で表していることを理解できると思う、と話してくれた。そして、深夜勤務の時に手浴をしたことを思い出してくれた。細くて白い指だった。そして冷たかった。15分間、お互いに何も話すことなく、ただただ手を洗った。沈黙の空間と枕灯の明かりの中、お湯の音だけが聞こえる。言葉は必要なかった。当時の自分ができる最大限の看護だったと話してくれた。30年間、心に思い続けるほどの問い。答えのない問い。色あせることのない問いを共有してもらった。
30年前、携帯電話も普及していなかった。今ほどスマホが普及していれば、お嫁さんともお話しできていたのだろうか・・・・・かもしれない。しかし、そのために余計不安になることもあるのではないか。もっと、話がしたいといって拘束してしまうことになるのではないか。そばにいてほしい、声を聴いていたい、その欲求に終わりはあるのか。依存は束縛となり、やがて二人は一人一人で立っていられなくなる。Aさんが亡くなった後も、生きていく人として、見守ることもまた看護であった。
そんな時、看護師は、患者の自立を支えながらも孤独でない距離感で、関心を寄せておくことが大事だ。さまざまな意見が飛び交う。
世代間による意向の違い、家族役割による意向の違い、さまざまな死に対する意向の「違い」を看護師は仲介役としての立場をとりたいものだ。それによって変わってくる治療方針や療養生活を多職種と連携していきたい。「その人らしく生きる」を支えることは「死ぬ」を豊かにするものでもある。
時代が変わっても、人間が死ぬことに変わりはない。本人はどう乗り越え、家族や友人もどう向き合っていくか、そして私たち医療従事者は、どんなプレゼンス(Presence)でいるのか。何度でも話し合いたい内容である。
古くても決して色あせない「死生観」について、世代を超えてディスカッションできたこと、とても有意義だった。
答えのない問いに1時間半語り合う贅沢な休日。参加してくださった看護学生、新人看護師、病棟看護師、訪問看護師、病児保育看護師、高校教員、医師、事例提供者の佐藤さん、本当にありがとうございました。

事例Aさんは本人を特定できないように、また文脈を損なわないように改良しています。