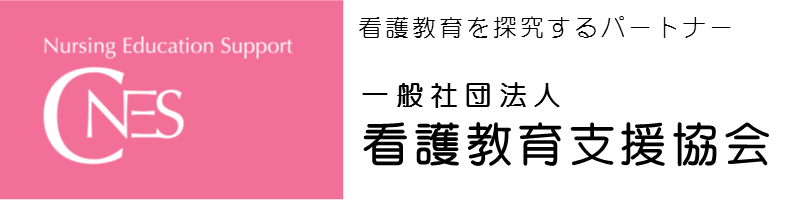幸せになる資格
頭でいくら理解していても、感情が追い付かないことがある。
Aさんは、食道がんからあちらこちらに転移をして治療を受けていた患者さんだった。経過は芳しくなかった。当時60歳代の男性だった。話をする間も、ときどき大きく肩で息をした。声も出ずらいときがあった。「私には、今の家族の前に、結婚はしなかったけど付き合っていた女性がいてね」と話し始めた。Aさんは、いつも上品な話し方をする。私は点滴を変えたりしながら、片手間に聴く話のようではなさそうだ。とはいえ、私が何かしているから話し始めた話かもしれない。「あら、」と言いつつ、手を止めずにさりげなく聴いていた。Aさんは個室だったから、二人だけだった。
「彼女は妊娠してね、」、うんうんと相槌を打った。私の心の中は、私に抱えきれるだけの話だろうかと不安に苛まれていた。
「でも彼女とは結婚できなくてね、うちの親に反対されてね、」、「ほう」、「彼女は、子どもは一人で育てると言って産んだけど、重い障害があってね。」、うんうん「で、女手一つで育てられないからと言って、彼女はその子を施設に入れてしまってね、」「お金で解決できる話ではなくてね、」
いよいよ私も手を止めて、ベッドサイドの椅子に腰を掛けた。私の器をはるかに超える話を聴く覚悟をした。
彼は腰を下ろした私のほうに顔を向けて「軽蔑するか?」と訊かれたので、黙って首を横に振った。声を失ったのは私の方だった。
「しばらくは施設に面会に行ったりした、けど、」大きな息をしながら「見てられなくてね、」と言って、鼻水を流した。しばらく、涙と鼻水を交互に拭いていた。私は、Aさんから次の言葉が出てくるまで待つ以外何もできなかった。
「それきり、彼女とも会わなくなって、あの子にも会いに行くこともなくなって、」、うんうんと相槌を打った。
「あの子は、私より早くに死んでいると思う、今の妻との間には、2人の子どもがいて、それなりに幸せだと思って暮らしてきた、幸せだと思えば思うほど、あの子のことを思い出してね、」
「自分は、幸せになる資格のない人間だと思って生きてきた、」
「癌になって、あの子を捨ててしまったことを許してもらえると思った、」
「って、頭で理解しても、なぜ自分だけがそんな思いをしなければいけないのかと思う、あの時、親さえ、結婚を許してくれていたら、二人であの子を育てていたかもしれない、悔しい」
「悔しいんですね・・・・」
「ん?悔しくない・・・・・情けない、惨めだ」眉間にぐっとしわを寄せて、指先にも力を入れた。
「少し寝よう、疲れた、看護師さん、忙しいと思うけど、眠りにつくまで、そばで座っていて欲しい」と言った。うなずいて、眠るまでそばに座っていた。眠りは浅く、すぐに目が覚めた。まだ、私はそばにいた。「本当にそばにいてくれんだ、まだ、生きてたね、」と言った。私はうなずいたが、立ち上がる暇もないほど短く深い眠りだっただけだった。
そしてそれ以上、「彼女」と「あの子」の話はしなかった。
人それぞれ、身体的な痛み、精神的な痛み、もっと奥深い痛みを抱えているものだ。そもそも「幸せになる資格」とは何だ?と考えるようになった。
Aさんは、主治医にも同じような話をしたらしい。「自分が死んだ後、研修医たち、看護学生たちに自分の遺体で学べるように提供したい」ということだった。そして、Aさんは痛みのコントロールを優先し最期を過ごした。
Aさんの亡くなった後、主治医は、研修医や看護学生に学びの機会をつくった。
Aさんが「幸せになる資格」を手に入れて、次の世界に行けたのならいいと思った。「あの子」に再会できていたら、あやまるよりも抱き合ってほしいと妄想にふける私がいた。

「看護」とは何かについて考えていくことを意図として、「看護師日記」を書くことにしました。私の看護師、看護教育の経験に基づいて表現していますが、人物が特定されないように、また文脈を損なわないように修正しています。