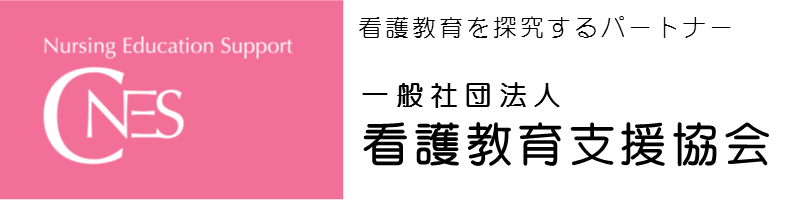コロナ禍、たった一人で過ごした寡黙な人
お義父さんはコロナ禍、面会もできず、一人で入院生活を送り、今年の2月に亡くなった。もうすぐ初盆を迎える。
コロナ禍、お義母さんと主人の二人だけが、少しだけ面会できたが、私もお姉さんも孫たちとも会うことができなかった。お義父さんは寡黙な人だった。だからと言って、自分の人生の終焉を誰とも共にすることなく、死んでいくことになるとは憶測に及ばなかったことだった。
お義父さんは老衰だった。棺から膝が飛び出すほど拘縮して屈曲していた。誤嚥性肺炎を繰り返すということで、口からは何も食べていなかった。あごの関節が拘縮して口が少し開いたままだった。会話できるほど口が動かなかったと思う。一人で静かに死の受容をしていたのだと思う。看護師さんや介護士さんは、そっと見守ってくれていたと思う。亡くなる日の朝、看護師さんが一人10分間ずつ会う時間を作ってくれた。私は、お義父さんにひたすらお礼を言った。これからのことも何も心配することもないことも言った。
お義父さんの思い出は、うちの実家の父がろくでもない人だったので、たいそう迷惑をかけたことから始まる。一言たりとも私に文句を言わなかった。実家の父は、結納の日も結婚式も出席してくれなかったが、お義父さんとお義母さんは、別の日に父に挨拶に来てくれた。
お義父さんは宮崎県出身で、小柄な人だった。小柄な背中を丸めて、父に頭を下げている後ろ姿を忘れることはできない。ろくでもない父の行動は記憶から葬り去った。ただ、お義父さんの丸まった後ろ姿だけは忘れることができなかった。
先日、私はお義父さんの故郷である宮崎県に行く機会があった。お義父さんと一緒に里帰りをした気分になった。高千穂町にある「天安河原」は、洞穴の中に小さな鳥居と社がひっそりとたたずんでいる。厳かな感じで足がすくんでしまった。「お義父さん!」と思った。
どんな偶然や必然が重なり合って、私はお義父さんと出会ったのかはわからない。お義父さんが愛した海や山、おいしい食べ物やお酒が脈々と受け継がれている。高千穂の夜神楽も楽しんだ。そういえば、お義父さんがいつも座っていたソファの横にお面が飾ってあったと思い出した。太鼓や笛の音は、郷土の子どもたちにとっても心が騒いだ音だったと思う。その音に合わせて自然と体が揺れていくのが神楽のリズムであり、しみ込んでいくように教育されていくのだ。
お義父さんは、私に看護師を辞めて育児に専念してほしいと思っていたと思う。それが、お義父さんが描いていた「家庭」だったように思う。
私が息子を生んだとき、お義父さんはたった一人で、大阪から和歌山の実家近くの産婦人科病院に息子の顔を見に来てくれた。うなぎ丼を持ってきてくれた。息子を抱き上げて、「ほうっほ~」と笑った。息子の名前も決まっていなかったので、「おい」と呼んでいた。そして私に「ありがとう」と言って去っていった。滞在時間1分30秒だった。
宮崎に来て思った。あの時、お義父さんが持ってきた「うなぎ」に意味があったこと。長いことかかってしまった。あの時名無しだった息子も結婚した。息子は宮崎県を知らない。お嫁さんと一緒に行ってほしい。じいちゃんに会えるから。
ありがとうございました。お義父さん。お盆にまた会いましょう。