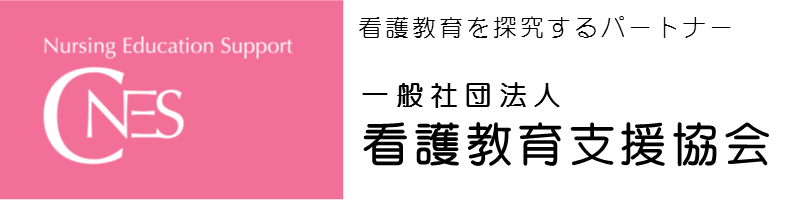看護師さんが声をかけてくれたけど。
私が高校1年生の時、祖父は半年間の入院生活の末、胸骨圧迫されながら死んでいった。
ベッドの周りは戦場のような有り様だった。40年前はまだDNR指示(do not resuscitation order)が確立されていなかったから、致し方のない状況だった。
廊下で私が泣いていると、看護師さんが声をかけてくれた。とてもやさしい声だった。
しかし、私が泣いていたのは、おじいちゃんが死んで寂しいからではない。
おじいちゃんは、私が子どものときに、戦争にいったときの話をよくしていた。ここちいいものではなかった。
たくさんの兵隊さんが目の前で死んでいったこと、食べるものがなく全裸になると肛門が見えるほど痩せたこと、海上で2日間ほど救助を待ったこと。おじいちゃんは膝の上に私をのせ、地球儀に指をさしながら、戦場となった国の名前を教えた。
おじいちゃんは、決して口にはしなかったが、生き残ったことに申し訳なさを感じているようだった。だから、つつましやかに、実直に働き、生き抜くことによって「善し」と誓ったのだと思う。
そのおじいちゃんが、医療という現場で生きることを請うただろうか。遺骨さえ帰ってこなかった兄の無念を背負い、最期の最期に何と戦わなければならなかったのか。その悔しさが、こみ上げてきたときのことを忘れない。
何処で死ぬか、どんな死に方をするか、何がいいか悪いかではない。
人それぞれの人生の最期、エンドロールが始まるときの選曲を間違えない看護、せめて邪魔にならない看護をしたいと思う。本人や家族、いろんなチームメンバーと話し合える時間や空間やプロセスを大切にしたい。そして、亡くなった後も、振り返ることを大切にしたい。
それらは受け入れ難く、近寄りがたいほど厳然である。しかし、そこに触れることのできる厳かな仕事でもある。

「看護」とは何かについて考えていくことを意図として、「看護師日記」を書くことにしました。私の看護師、看護教育の経験に基づいて表現していますが、人物が特定されないように、また文脈を損なわないように一部修正しています。