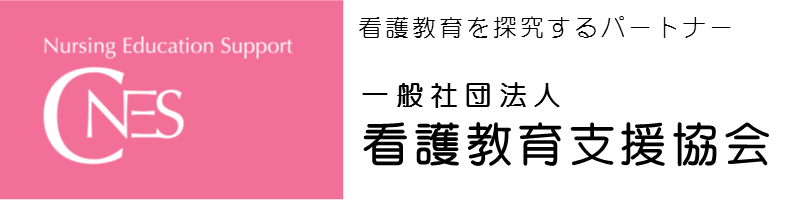子どもたちの健康と安全を支える新たな一歩
このたび、キャンプナース®として初めて、支援学校の課外活動(小学部5年生の宿泊学習)に引率し、子どもたちの健康と安全を支える役割を担いました。
2日間、仲間と共に過ごし、規律ある集団生活を体験すること、そして家族と離れて自立心を育むことを目的としたこの学習活動に、さまざまな支援ニーズを持つ子どもたちが参加しました。その貴重な学びの時間に同行できたことは、大きな経験となりました。
活動内容とケアの概要
今回の宿泊学習には、男児・女児あわせて10名が参加。教員、看護師、養護教諭と連携しながら、医療的ケアが必要な子どもたちへの支援を行いました。
-
胃瘻管理:食事は経口で摂取し、水分と薬を胃瘻から注入
-
人工鼻使用:喀痰吸引への対応
-
酸素療法(HOT):就寝時に1.5Lの酸素を経鼻カヌラで吸入
-
入浴前の浣腸、入浴後の軟膏塗布、胃瘻部・気管切開部のガーゼ交換など
また、当日には発熱やカニューレの自己抜去といったトラブルも発生しましたが、ご家族や教職員との密な連携により、臨機応変に対応し、安全に宿泊を終えることができました。
保護者と教員との連携
保護者の方々が詳細に記入されたケアシートをもとに、教員から「指示どおりに対応を」と助言される場面がありました。
たとえば、注入の際には「薬は白湯で、お茶は水分補給用」「150mLきっちり」など、細かい指定がありました。こうしたケアの厳密さと現場の柔軟性の両立には難しさを感じつつも、このバランスがお互いの信頼関係を支えているのだと実感しました。
気づきと次回への課題
夜間、眠れずに走り回る子どももいましたが、キャンプナース®への呼び出しはありませんでした。
今回の経験から、身体的ケアだけでなく、子どもたちの“心の動き”にも目を向けられるよう、事前のチーム内での情報共有や役割分担の明確化が今後の課題であると感じました。
また、振り返りの機会を持てなかったのは残念でした。次回の事前打ち合わせでは今回の経験をもとに、改善点を提案していきたいと思います。
子どもたちの笑顔、先生たちの思い
言葉でのやり取りが難しい子どもが多く、自傷行動が見られる場面もありました。しかし、活動の合間にはたくさんの笑顔が見られ、先生たちの寄り添う姿勢が非常に印象的でした。まるで保護者のように愛情深く接する先生たちの表情や言葉には、子どもたちへの深い思いが溢れていました。
レクリエーションでは、先生たちと一緒にジェルキャンドル作りを楽しみ、子どもたちはそれぞれの方法で活動に参加していました。雰囲気づくりの工夫も相まって、場にいる全員が温かさを感じるひとときとなりました。勤務外に子どもたちに会いに来る先生が多く、学校全体が「チーム」として子どもたちを支えている様子が伝わってきました。
キャンプナース®の新たな役割と展望
今回の取り組みは、キャンプナース®にとって“新たなフィールド”での挑戦となりました。
医療的ケアや障害のある子どもたち、そのご家族や教職員と連携しながら、安心と楽しさを届ける存在として、私たちキャンプナース®が果たせる役割の広がりを改めて実感しました。
今後、このような活動がさらに広がり、すべての子どもたちが安心して学び、体験を楽しめる環境づくりに貢献できるよう、今回の学びを次につなげていきたいと思います。
レポート キャンプナース® 池田 光余