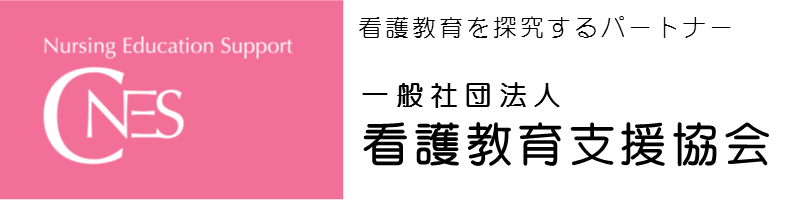やることがないと言って遊んでしまう子・・・・・
昨日、ある団体の寄付による地域の歴史探索キャンプに、キャンプナース®として参加しました。このキャンプには普段あまりキャンプを経験したことのない、新小学1年生から新中学1年生までの45名の子どもたちが参加しました。擦り傷、転倒、打撲、アレルギー性の目のかゆみ、嘔吐、火傷、おねしょなどの対応はありましたが、幸い大きな怪我や事故はなく、無事にキャンプを終えることができました。
初めてキャンプに参加した子どもたちは、キャンプならではの体験に戸惑う場面もありました。その中で、火ばさみを素手で触ってしまい、やけどを負った子どもがいました。キャンプ経験の豊富な子どもならばすぐに流水で冷やすという行動ができますが、初めての子どもは火傷の対応は知らなかったようで、痛みを感じて初めて私に伝えることができました。水疱ができましたが痛みは落ち着き、その後の活動には元気に参加できました。この子どもは一つ大きな学びと体験を得たと言えます。
キャンプに参加すると、いつも感じることがあります。それは、熱心に調理などのお手伝いをする子どもと、「やることがない」と言って遊びに行ってしまう子どもがいるということです。その光景を目にしながら、喜多川泰さんの著書『ライフトラベラー』を思い出していました。
その本の中で「お手伝いをすると100円もらえると決めてしまうと、100円より安いと感じるお手伝いはしなくなる。つまり、体験することを損得で考えるようになる」といった内容が書かれていたからです。
体験することによって何が得られるのか、それが自分の得になるのかを考えるよりも「誰かの役に立っているか」を考えて行動できる子どもに育ってほしいと私は願っています。そのためには、目の前の体験をとことんやり切ることが重要だと感じています。
「やることがない」といって遊んでしまう子どもたちは、将来、どんな大学に通って、またどんな仕事をしたとしても、「何をしたらいいかわからない」「私らしさって何?」と言い出すのではないかと懸念を抱いてしまいます(笑)
これは私たちキャンプナース®にも同じことが言えます。キャンプナース®の役割を損得やコストパフォーマンスで考えると、本当に得られる大切な体験は見えなくなってしまいます。私たちの最上位の目標は、子どもたちが安全かつ健康にキャンプを楽しみ、無事に家に帰ることです。「何ができるのか」という体験に没頭することが大事です。
ゴミを拾う、靴を並べる、トイレが清潔かを確認する、部屋の換気をする、睡眠環境を整える、服装の調整や水分補給といった一見さりげない行動も、子どもたちの健康や安全につながっています。キャンプナース®として重要なのは、子どもたちの主体性を奪わず、自尊心を傷つけない見守りを通じて、子どもたち自身が自ら考えて行動できる環境を整える体験を私自身が没頭することです。
キャンプナース®という役割を通じて得られる喜びややりがいを、ぜひ多くの看護師さんに体験していただきたいと思います。看護の基本に触れる体験ができると思います。