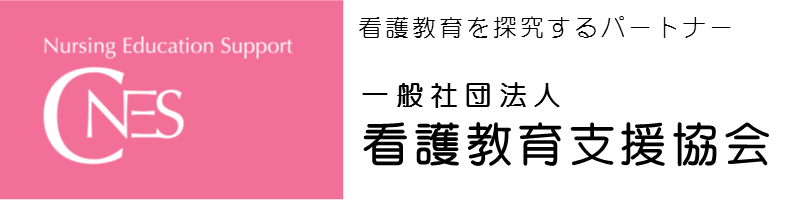10年後の看護
看護師さんは「忙しい」という。あと10年たっても忙しいのだろうか。
少なくとも、バイタルサインの測定や採血の仕事は、技術が進歩して「古(いにしえ)」と葬り去られている。この話は10年前にもしていたが意外としつこく残っていた。しかし、変化は突然訪れた。非接触タイプの検温カメラが普通になった。ずいぶん昔からあったが普及していなかった。コロナで必須アイテムとして社会に浸透した。急にその日が来たのだ。
採血やカテーテルを挿入する検査もあるが、唾液や尿など簡易に健康状態がわかるもの、身体や精神状態が可視化できるスキャナもどんどんできていく。厳密にいえばできている。ただ、何かの事情で商品化に至っていないものもある。商品化すれば、看護師さんも時間にゆとりができるのではないかと思う。
その代わり、脈拍を測定し、脈拍数ではなく「どんな感じ」とか、顔色を見て「どんな様子」とか、体温を肌で感じて「あれ?」とか、と言う微妙な力は、ますます必要となる。対象となる人の身を置いている環境を個性に応じてより快適なものに整えたり、その時間を共有したり、その思いを理解したり、持て余した時間を価値がある時間に変換することを支援したり、「看護」の本質を打ち抜く選りすぐりのみが残っていく。50年以上続いた「看護技術」といわれるテクニカルスキルは、どんどん変化して、時には風化して、本質的なもの「技術(art)」が露出する。
そうそう。この前、私は夜空を見上げていた。雲がかかっていたので、月のない夜空だった。しかし、明らかに雲の色が違うところがあった。「あの雲の向こうに月がある」と思った。しばらく、夜空を見上げていた。どんどん雲が黄色さを帯びてきた。やっぱり、そこに月があったのだ。雲は流れていた。そして月が現れた。「おう」、私のこころは喜びの声をあげた。急にその時が来たのだ。
月は見えるか見えないかだけだ。地球と月は法則に則って存在し合っている。再確認した。
看護も同じだ。病気や症状が見えているか、見えていないかが重要ではない。「私」と「あなた」の間に、確実にあるものなのだ。看えるところに立つ。聴く。触る。日常の中の「ある」に気づく。看護をするということだ。
しかし、世界中どこを探しても、ひいばあちゃんや祖父母、父、お義父さんやお義母さんはいないのだ。同級生も何人か他界している。世界中どこを探してもいない。そう思うと下を向いてしまいそうになる。しかし、記憶としてある、そればかりか「教え」として残されたりする。やはり、あった、ある、あり続けるのだと思った。あるというのは、すべて「私」が創りだすものだった。その時、その時を私が創り出している。