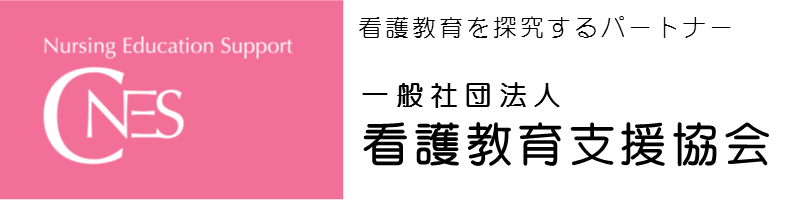劣等感が結核の石灰化巣陰影のように残っている
私は、現職に就いてから、しばらく白衣を着ることはなかった。
しかし、コロナ禍、実習指導や学内実習などなど、実習にまつわる仕事も舞い込んできたので、白衣を着ることがあった。
そこで気づいたこと。私は、白衣を着ると緊張する。身が引き締まるというかっこいいものではない。緊張しているのだ。小動物が心臓をバクバクさせながら、「私で大丈夫?」といっているような緊張である。
そうだ。私は、看護師という仕事をすることに劣等感を持っている。私は、「できない看護師だ」と自分で思っている。それは、人生の忘れ物のようにいつまでも私のこころにくすぶり続けている。教員をしているときは、その劣等感が怒りに変わったことが度々あった。「それをやったら、私みたいにダメな看護師になるよ」とでも言っているような悲しみや焦りの感情だ。
今回も同じように、白衣を着ている自分に緊張感と「~しなければならない」という焦りが湧き出してきていた。
なるほどなるほど。間違いない。わたしは、私の劣等感を隠そうとしている、ごまかそうとしている。
白衣を着る自分は、過去におこったいろいろな出来事、例えば、患者さんにまつわること、人間関係にまつわること、日常の病院で起こる命の誕生、障害、病気、健康回復、喜びの退院、慢性化、悪化、急変、死・・・・・・、その感情の渦を抱えきれていなかった。目を背けたかった。押さえつけて必死に隠していた。抱えきれていなかったことが分かっていて、みんなで協力する力もなかった、そして頑張り抜くこともできなかった、それが結核の石灰化巣陰影のようにこころに残っていたのだ。
石灰化したものを無理に除去しようと思ってはいない。私にとって、病院の看護は、当時の自分には扱いきれなかったのだ。今も扱いきれないと思う。
私は、これから何ができるか。話し合ったり、何かを学び合ったり、模索したりしながら歩んでいくことはできる。それは、看護基礎教育、看護師教育、キャンプナース、地域精神看護・・・・いろいろある。
また、白衣を着ることもある。その時は、また小動物のように緊張する。それでも、私のできることを粛々とする。それだけだ。
ただ、自分の劣等感を隠すために、その感情を違う形で表現しない。しそうになったり、気づいてやり直す、話し合う。やってしまったら、謝る。そしてやり直す。これさえ繰り返しできていけば、そのうち、私の中にある石灰化した劣等感は、私自身に承認されるようになる。
特に、患者さんやご家族、若者やまだ慣れていない人、海外からきて働いている人、つまり、まだ弱い人たち。可能性を一杯秘めているのにもかかわらず、たった今「知らない」「慣れていない」と言う理由で、十分に発揮できていない状態の人を、何か「足りない」と言って私の劣等感をぶつけない。自分が叶えられなかった夢を子どもたちに押し付けてはいけない親のようなものだ。
今頃気づいたのではない。早くに気づいていた。ただ、公にできなかっただけだ。こうして、公言できる場があってよかったと思う。
患者さん、学生さん、新人さん、日本に来て間もない医療スタッフは、何かが「足りない」のでははない。私が予測する「伸びしろ」でもない。何者にでもなれる可能性を秘めた存在である。