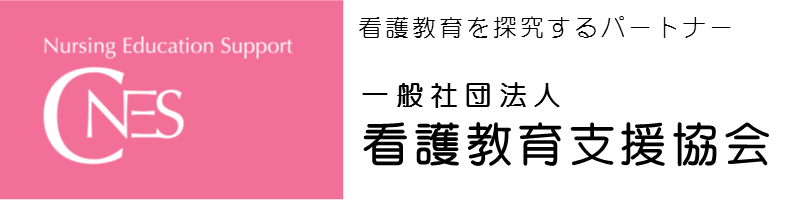まだまだ、目を凝らしてみなければ見えない世界がある。
藤ノ木優さん(現役医師)の『-196℃のゆりかご』は、現代の生殖補助医療をテーマに、家族や血縁、出自に関する葛藤を描いた作品です。主人公・つむぎが、育ての親である奈緒が実の母親であることを知ることをきっかけに、母娘の関係や長年の嘘に込められた真意を探っていきます。
日本の少子化問題が本格化する中で、生殖補助医療は家族を持つための大きな選択肢のひとつになっています。共働きが当たり前になった日本で、結婚するのか、しないのか、子どもを産むのか、産まないのか、仕事を続けるのか、続けないのか、選択肢は多様になりました。しかし、「欲しくても授からない命がある」「欲しくなくても授かる命がある」、そして医療の進歩とともに生殖補助医療は「欲しい」と願う人に希望をもたらしていると思っていました。ただ、生まれてから、どう育てるか、自分(親)の人生の何を優先するのかが、時代の潮流とともに翻弄され、そのたびに、関係性を柔軟に軌道修正していくことを迫られてきたのだと思いました。
体外受精や凍結胚移植などの技術が普及し、それを利用する人々の権利や心のケアが十分に守られていない状況や、社会の理解がまだ追いついていないことも否定できません。
少子化対策の生殖補助医療が推進されつつありますが、同時に家族や血縁の在り方が再定義されるべき時代がきています。「家族とは何か」「子どもを持つことの意味とは何か」を深く考えさせてくれる一冊でした。