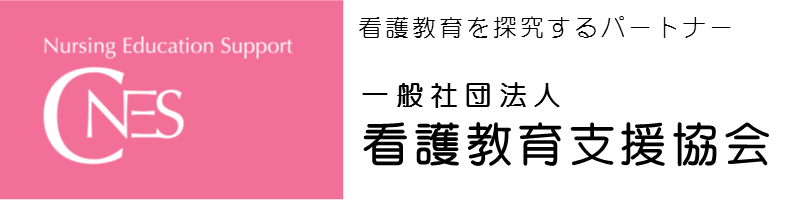食事介助
看護学生が実習に行けば、必ず、食事介助をさせてもらうAさん。Aさんは90歳代の女性だ。認知症のため、失語、失行、失認があり、食事を自分で行うことが困難だった。嚥下は問題なかった。関節の拘縮があり、座位の保持が困難で、クッションなどを置いて工夫しても、車椅子から落ちそうになる。だから、車椅子に移動するときは少しリクライニングを倒していた。
看護学生がかわるがわる食事介助を体験させてもらった。施設ならではの体験だった。
出会ったころは、Aさんはすぐに食器をひっくり返してしまうので、Aさんと握手をしておく役割の私と食事介助をする学生の二人体制だった。でも、配膳の位置を考慮するだけで、私の任務はあっけなく終了した。
何をお話しされているかはよくわからないが、何かお話ししてくれているように伝わってくるので、学生はうなづきながら何かを感じ取っていた。学生がうなづくとAさんもうなづいた。年齢差40歳の間でどんな会話が成立しているのか興味深かった。
特にAさんは、デザートが好きだったので、お粥の合間にデザートを欲しがっていた。お粥の合間にプリンを口に運ぶ学生もいれば、「Aさん、プリンはデザートなので最後ですよ」と説明する学生もいた。確かにプリンを食べているときのAさんは至福の表情をしてくれた。私個人的にはお粥の合間のプリンは反対派だが、Aさんはどっちでも最後まできちんと食べてくれた。
そのうち、少しずつ座位がとれるようになった。寝ているAさんの顔と座っているAさんの顔はまるで別人のようだった。Aさんは、こんなお顔をしていたんだなと思った。すっきりとした表情をしている。しかも笑顔だ。確かに寝ころんだまま笑うのは難しい。
そして、いよいよ自分でスプーンをもって、ご飯を食べることができるようになった。少しこぼしてしまうこともあるが、しっかりと自分で食事ができている。同じものばかり食べてしまうので、お皿をみえやすい位置に動かすサポートは必要だ。そのサポートだけで完食できるようになった。学生は、お話をする中華料理店の回転テーブルのような役割となった。ナイス看護だ。
高齢になって認知症があると、どうしても現状維持、あるいは悪くなっていくことを考えてしまいがちになる。しかし、一時的に体調を崩しただけで実は認知症自体がそれほど進行していないこともある。実際に働いている看護師さんたちは、自分で食べてもらおうかの判断、やっぱり介助にしようかの判断。そして実践、判断、実践、判断の連続だ。
加齢かつ慢性的な病気や障害があっても、現状維持か悪化の2択ではない。一時的に悪化したように見えることがあっても、それは症状であり、回復過程をたどるという視点を忘れてはならないと思った。
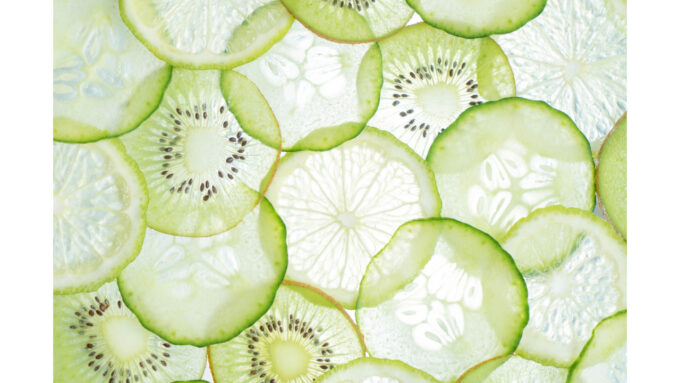
「看護」とは何かについて考えていくことを意図として、「看護師日記」を書くことにしました。私の看護師、看護教育の経験に基づいて表現していますが、人物が特定されないように、また文脈を損なわないように修正しています。