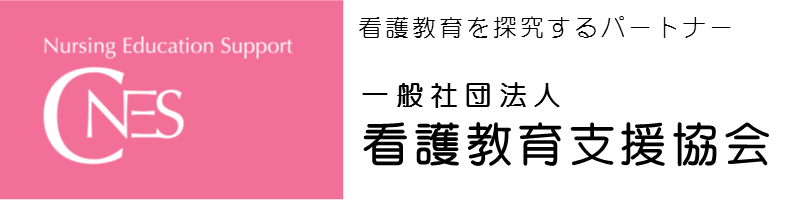異文化に触れることは、自分を知ること。
まずチュニス空港からケロアンに移動しグランドモスクに行きました。入館の際には髪の毛を隠すことを求められました。
ヒジャーブの生地や色など、こうあるべきだという統一されたスタイルはないようです。現在、世界ではヒジャーブの着用スタイルは個人的な好みのようです。頭と首を覆っているが顔は隠さない「ベール」と呼ばれるものが主流のようです。ただし、ヒジャーブとは、正式には手、顔、足元を除くすべてを、長くて緩く、透けて見えない衣服(体の線が見えない)で完全に覆うことを意味しています。

1. チュニジアの宗教と人々の暮らし
1-1. スンニ派イスラムが主流
チュニジアは国教はイスラム(スンニ派)です。街を歩いていると、白いミナレット(モスクの尖塔)があちこちに立ち並び、礼拝の時間にはアザーン(礼拝への呼びかけ)が聞こえてきます。イスラムと聞くと厳格なイメージを抱かれる方もいるかもしれませんが、実際に触れたチュニジアの暮らしは穏やかで親しみやすい雰囲気でした。
-
礼拝(サラート)の時間
1日5回の礼拝時間には多くの方が仕事や家事の合間を縫ってモスクに集まりますが、すべての人が必ずモスクへ行くというわけではありません。職場や自宅で静かに祈る人も多く、それぞれの生活リズムに合わせた信仰スタイルが見受けられました。街中で、お祈りをしている人を見かけませんでした。「あら、こんな感じなんだ~」と逆に拍子抜けしたほどです。といっても、大切な時間であることには違いありません。 -
イスラム教の最も重要な聖典(コーラン)であり、ムハンマドが23年間にわたって天使ジブリールを通じて受けた神の言葉の集大成です。アラビア語で記され、その言葉は神の直接の言葉であると信じられています。コーランは神と人間の関係、社会生活の規範、崇拝行為の指針などが含まれています。つまり、礼拝は、神と人間が結びつく時間と空間であると解釈しました。
1-2. 多様性と共存
チュニジアは大多数がイスラムを信仰する一方、長い歴史の中でユダヤ教やキリスト教など他宗教コミュニティが存在してきたこともあり、比較的寛容な雰囲気があります。街を歩いていても、観光客や他国から働きに来ている人々など、多国籍な人々がおられます。
チュニジアはアフリカ北岸、マグリブ地方の中央部にあります。中心都市は空港のあるチュニスです。その近郊には古代カルタゴの遺跡があります。かつてカルタゴ帝国として栄えました。しかし、ローマとのポエニ戦争ではカルタゴの町は徹底的に破壊され、その結果、この地はローマの属州となりました。
現在のチュニジアになるまでに何度も戦争を繰り返し、多くの国の影響を受けてきました。大きな大陸の一部の国でありながら、地中海に面しているため、海を使った貿易が盛んだったことも多様性を受け入れる環境にあったようです。
2. 歴史と文化
2-1. 私が訪れた世界遺産
-
エル・ジェム円形闘技場(El Jem)
ローマ時代の壮大な円形闘技場。外観の保存状態が非常に良く、まるでローマ時代にタイムスリップしたかのような感覚を味わえます。ヨーロッパのコロッセオより規模は小さいものの、その迫力は圧巻で、ローマ帝国の影響の大きさを実感しました。 -
ドゥッガ遺跡(Dougga)
遺跡全体が丘の上に広がっており、劇場や神殿、公共施設跡(浴場やトイレ)などが残っています。下水路が発達していたため、ところどころにマンホールを思わせるような石がありました。当時の技術力の高さを感じました。 -
カルタゴ遺跡(Carthage)
古代フェニキア人が築き、後にローマと覇権を争った都市の遺構です。ローマ風呂や円形闘技場跡などが点在し、その歴史の断片を垣間見ることができます。首都チュニスの近郊にあるためアクセスも良く、古代から続く文明のレイヤーを身近に感じられるスポットです。
2-2. ベルベル(アマズィグ)文化の足跡
北アフリカの先住民族とされるベルベル(アマズィグ)民族は、チュニジアにも古くから住んでいました。現在ではアラブ化が進み、ベルベル系住民の人口は少数派だそうです。南部や山岳地帯には今もベルベル語を話し、独自の生活様式を守って暮らすコミュニティがあります。
-
マトマタやシェニニの洞窟住居
地下や山肌をくり抜いて作られた伝統的住居は、観光地としても人気です。ベルベルの人々が厳しい暑さを凌ぐための工夫であり、独特の景観に圧倒されました。 -
伝統工芸や音楽
アラブ文化とは異なる模様や色使いの織物、アクセサリーなどがあり、地域性がとても豊かです。現地の音楽は打楽器を多用し、軽快ながらもどこか神秘的な雰囲気を醸し出しています。
3. チュニジアならではの暮らしや習慣
3-1. スーク(市場)での買い物
旧市街(メディナ)の細い路地に所狭しと並ぶお店や露店。フランスの植民地であった歴史と関係があったのかどうかわかりませんが、フランス通りと呼ばれており、ミニ凱旋門もあります。
そこでは様々なスパイス、伝統工芸品、日用品などが売られています。地元の人々は当たり前のように値段交渉をするので、私も最初は戸惑いました。まず、何を言っているかわからない(笑)
結局、玄関マットを購入しました。
3-2. チュニジア料理と食習慣
- クスクス
蒸した小麦粉に肉や野菜を煮込んだ具材を盛り付けた、マグリブ地方を代表する料理。チュニジアのクスクスは唐辛子ペーストであるハリッサを使ったピリ辛な味付けがされています。まずくはないのですが、何かが足りない・・・・そんな印象を持ちます。 - ハリッサ
さまざまな料理に使われる赤唐辛子ペースト。パンに塗ったりスープに入れたりと、チュニジア人の食卓には欠かせない存在です。これはさすがに辛いです。私は、辛さに強いですが、パンに塗って食べたいとは思いませんでした。 - ブリック
薄い小麦粉の皮で卵やツナ、玉ねぎ、パセリなどを包んで揚げたスナック。揚げたてのパリパリ食感がたまりません。本当においしいです!家でも作れそうな家庭料理です。
基本的にイスラム教の国ですから、アルコールを置いていないレストランもあります。滞在中は、豚肉は食べませんでしたが、鶏肉、イノシシはいただきました。
アルコールを置いていないレストランもあるというだけで、スーパーに行けばいくらでも購入できます(笑)
3-3. カフェ文化
カフェで甘いミントティーやコーヒー(トルココーヒーみたいな感じ)を飲みながら、おしゃべりを楽しむ姿もよく見かけました。特に、ミントティーを飲みながら、水タバコ(シーシャ)をゆっくり吸い、長い時間談笑するのがチュニジア流だそうです。しかも、カフェを利用しているのは男性ばかり。働かなくていいのかしら?と思うほどですが憩いの場だそうです。
女性がいないのは、「カフェ」は男性のいくところといった特に疑わないような「当たり前」があるようです。疑わない当たり前は、日本の各地にありますよね。
チュニジアの人が日本に行って驚いたことは、電車の時刻表が「14時23分」とか、分刻みになっていることに驚いたそうです。チュニジアでは大体、8時半ぐらいかな~だそうです(笑)まず、電車(鉄道)が、1本だけなんです。移動はバス!
4. ベルベル文化と観光と今後
南部の洞窟住居やベルベル集落は、チュニジア観光のスポットでもあります。しかし、観光客が押し寄せることで、文化が「お見せするもの」とされてしまうリスクも否定できません。ガイドさんに伺ったところ、「観光収入は大きな助けになる一方で、本来の文化や習慣が失われてしまわないか不安もある」とのことでした。
同時に、若い世代の都市流出やアラビア語の普及により、ベルベル語を話せる人が減っているという課題もあるそうです。チュニジア政府や市民団体が、ベルベル語や伝統文化を見直す取り組みを始めていると聞き、少数民族の文化が守られながら発展していくことを願わずにはいられません。
砂漠化を防ぐために植林をし、また、岩を掘って住居にするという自然との調和が「生き延びていく」というたくましさを感じました。
チュニジアの内陸部には、「ショット(Chott)」と呼ばれる塩湖地帯が点在しています。トズールやドゥーズなどのオアシス都市の周辺に広がっています。
-
塩の結晶が作り出す白い大地
雨が少ない地域では湖の水が蒸発し、地表に塩の結晶が広がります。まるで雪原のような真っ白い大地がどこまでも続く景色は、一見の価値があります。特に日中の日差しが強い時間帯は、太陽の光でさらにきらめき、幻想的な雰囲気に包まれます。
人間、動物(ヤギ、ヒツジなど)、またオリーブの木をはじめとする草木は、厳しい環境に適応し、また変態し、文化を創り出してきました。そこにはそれをする必要性があったのです。
観光産業とは、何かを売る、何かを楽しむことのほかに、脈々と続いた大切なもの(価値・その土地に必要だった自然との調和)を知る、残すという役割があると思いました。
エル・ジェムやドゥッガ、カルタゴ遺跡など世界遺産に登録された場所は、観光客を惹きつける一方で、遺跡の維持や保護のための費用や取り組みが欠かせません。観光産業の発展と遺産保護のバランスをどう取るかは、チュニジアに限らず日本に共通する課題です。
5. まとめと私が感じたこと
チュニジアを訪れる前は「地中海と砂漠の国」というイメージしか持っていませんでした。しかし、現地を巡ってみると、何層にも重なった歴史と文化が今でも息づいています。
あちらこちらに「TOYOTA]の車が走っています。鉄道はあえてつくらず、道路整備をすることで、比較的自由な車社会が出来上がったようです。乾燥した気候と車の排気ガス、健康的ではありません。日本人はマスクをしているからわかるとおっしゃっていました(笑)。私は、マスクをつけていない日本人なので、街中では「アンニョンハセヨ(안녕하세요)」や「ニーハオ(你好)」と声をかけられました。
- 宗教について学んだこと
スンニ派イスラムが中心である一方、他文化・他宗教との交流を大切にする寛容な社会がある。 - 文化と暮らしについて学んだこと
アラブ文化と先住民族ベルベル文化が交差し、多様な伝統や習慣が今も受け継がれている。 - 観光と伝統のジレンマ
観光資源として魅力的なベルベル文化が摩耗される一方で、その文化と言語を守る動きもある。
短い滞在でしたが、チュニジアが持つ奥深さは私の想像をはるかに超えていました。もしこれからチュニジアを訪れる方がいらしたら、首都チュニスのメディナやカルタゴ遺跡だけでなく、南部や山岳地帯へ足を伸ばして、ベルベルの人々が営む暮らしを垣間見ることをおすすめします。
異文化に触れることは、「私を知る」「日本を知る」ことにつながります。それは「違い」を通して、自分を表現しようと試みるからです。
日常の他者との会話を丁寧にやっていれば、いいことなんですね・・・・(^^♪
私をアフリカ大陸にまで連れていくことに協働してくださったすべての皆様に感謝です。
最後までお読みいただきありがとうございました。