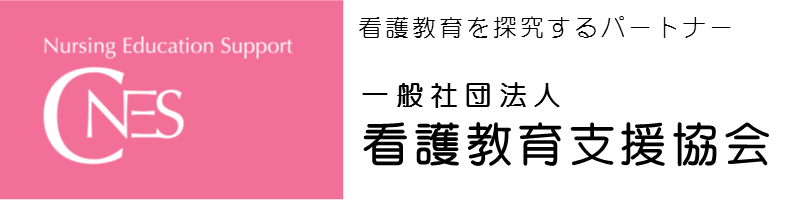私が看護師を選ぶまで
私には5歳年上の兄がいる。兄は実家のみかん農家を継いでいる。
私が高校生の時、兄は激しい倦怠感がありみかん山から帰ってきた。2,3日寝込んでいた。
昼下がり、おばあちゃんは、近所のお茶のみ友だちと縁側で甘いインスタントコーヒーを飲んでいた。兄がたまたま怠い体を奮い立たせて、部屋からトイレにむかって歩いていると、その様子を見かねて「たかちゃん、どうしたん?」と声をかけた。「体調が悪い・・・」と面倒くさそうに答えていた。茶のみ友だちは「たかちゃん、あんたの目、黄色いわ!」とやや大声で言った。おばあちゃんも「あれ?ほんまや!」と言って背筋を伸ばして兄の目を凝視した。
急展開となった。そのまま病院に行った。ただ誰がどうやって兄を病院に連れて行ったのか、そこからの記憶が嘘のように消えている。
兄の病名は劇症肝炎。青天の霹靂であった。
その日から兄は、病院のベッドで安静の日々が続いた。今は、代々続いているみかん農家を担うことができているが、命を落としかねない状態だったらしい。肝臓の病気を学ぶたびに「無知とは怖いことだ」と悟り、鮮烈に兄を思い出す。
私は、兄の容態が落ち着き面会ができるようになってから、セーラー服のままお見舞いに行った。兄は、本を読むのが好きだったので、好きそうな本を選んで持って行った。しかし、表紙を見ただけで床頭台にポンと置いた。「え、せっかく買ってきたのに、読まんの?」「あんまり、読む気にならん」。その時は「絶対、買って来てやらん」と思ったが、今思えば、本を読む気にならないほど倦怠感があったのだ。それにしても、兄はこんな病院臭いところで、よく寝起きできているなと感心した。私は自分のセーラー服が臭くなるのではないかと心配になり、あまり長く居ないほうがいいと感じた。
看護師さんが入ってきて「今日は、妹さんが来てるのねえ~」と声をかけてくれた。点滴を取り換えたり、血圧を測ったり、兄の体に聴診器を当てたりしていた。看護師さんはいくつか質問をしていて、兄は不愛想に答えていた。もっと愛想よくできないのかと思った。しかし本当にしんどかったのだ。
そんなベッドサイドでの二人のやりとりをぼんやりと見ていて、白衣の真っ白さとナースキャップの凛々しさ、所作の無駄のなさが単純にカッコイイと思った。
一番カッコイイと思ったのは、部屋から出ていくときの後ろ姿だった。姿勢の良さとほっそりとしたウエストと、白いパンストをまとったきれいな足が印象的だった。
昭和の終焉の頃だった。自分の進路を決めていく時期に、自立した女性、女性として働き続けること、自分らしさを表現することを 教えてくれた無言の後ろ姿だった。
私は美術大学に行こうと思っていたのでデッサンを始めていた。しかし、その後ろ姿に自分の進路が揺れ動かされ、胸がドキドキしたことを覚えている。
看護師の仕事にあこがれたということは全くない。どんな仕事をするのか知らなかった。ただ、一人の女性として、人として、自分を表現していく機会を得られる仕事なのではないかと感じた。
私は、兄のいる病院から帰ったあと、汗と病院臭くなったセーラー服を洗濯機に放り投げた。そして、またデッサンを始めた。高校2年生の真夏の出来事だった。