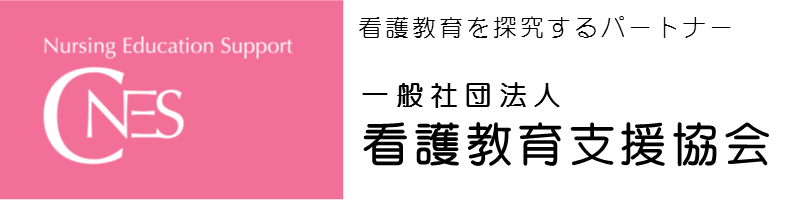2025年11月、2泊3日、瀬戸内海に浮かぶ無人島で開催された子ども向けキャンプに、キャンプナース®として参加した。
無人島という特別な環境の中で
無人島キャンプは、子どもたちが自然の中で生活し、協力しながら課題を乗り越えるプログラムである。医療機関もコンビニもない、まさに「自分たちでつくる生活」。
その中でキャンプナース®として私が担ったのは、体調管理と衛生面のサポート、そして安全な環境づくり。
上陸早々の洗礼、突然の大雨!そして雷!
急いで子どもたちを大学生ボランティアと一緒にブルーシートの中に避難。
絶対濡らしてはいけない備品は速やかにテントを立てて、その中にとりあえず投げ込む込む。
すでに不安そうな顔になる子どもたち。でも船はないし、Wi-Fiもないから「もう乗り越えるほか選択肢はない」と覚悟する顔に変わっていく。
その後の夕飯づくりは、地面はぬかるんでいるし、持参した新聞紙が湿っているし、拾ってきた木っ端も濡れているので、ご飯が炊けるほど火がつくには2時間もかかった!(炊飯器様、ありがとう!!という気持ちになる。)
島の夜は、驚くほど寒く、私は寝袋と毛布が必要だった。日中は、日差しのある所は暑いが木陰は寒いくらい。体温調節できる衣服が必要だ。汗をかきすぎたままにしておかないことも観察事項だった。
虫刺され(体長20cmのムカデを2匹駆除した。ムカデが出ると私も呼ぶのはなぜか?笑笑)、疲労、睡眠不足など、子どもたちの体調は常に変化する。水分補給、食事のバランス、温度調節、衛生環境を整える——すべてが“看護”そのものだった。
自然の中で気づく「看護の原点」
無人島での3日間は、医療行為よりも「予防」や「環境整備」が中心だった。
体調を崩す前に気づくこと、そして未然に防ぐことの大切さを実感した。
また、子どもたちが安心して挑戦できるように、ただ見守り、環境を整えるというキャンプナース®の存在意義を感じた。
安全を「守る」だけではなく、「生きる力を育てる」こと、自然体験の場での看護の醍醐味だ。
活動を通して見えてきた課題
今回の経験から、いくつかの課題も見えてきました。
- 情報共有の仕組み:体調記録やスタッフ間の連携方法を明確にしておくこと。
- 気象変化への備え:気温差・雨天時への対策を具体的にシミュレーションすること。(例えば、悪天候で船が迎えに来られないという場合の食料や衣類の調整。雨の後のぬかるみや滑りやすさに対応できる靴。潮の満ち引きの把握によっておこるリスクなどなど)
これらは次回以降のキャンプや他の現場にも活かせる大きな学びとなった。
今後に向けての提案
キャンプナースは、子どもたちの健康教育の担い手としての役割を果たす存在。
- キャンプ前に子どもたちと行う「健康教育プログラム」
- スタッフ全員で行う「体調変化対応シミュレーション研修」
- 地域の医療機関や看護教育機関との連携体制づくり
- 看護学生や教育関係者が参加できる「実践型キャンプナース研修」
無人島という限られた環境だからこそ、そこには“生きる知恵”と“支える看護”が凝縮されていた。
おわりに
今回の無人島キャンプでの活動は、看護の原点を見つめ直す貴重な機会となった。
体調を守ることはもちろん、子どもたちの「挑戦を支える(成長を見守る)」ことも、キャンプナース®の使命である。